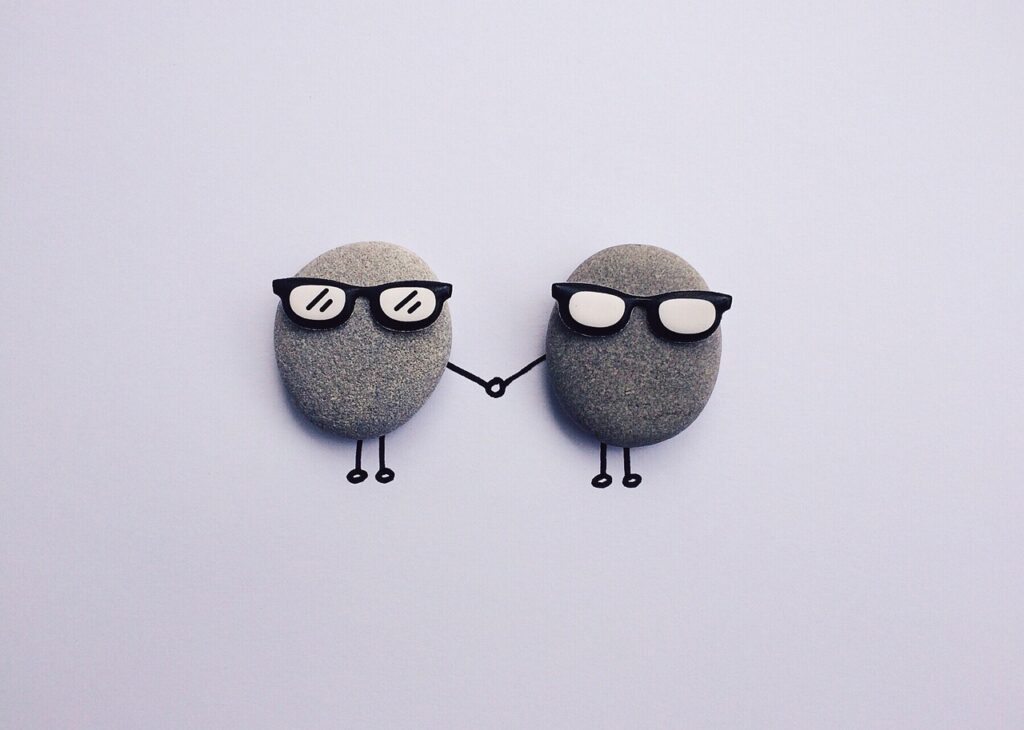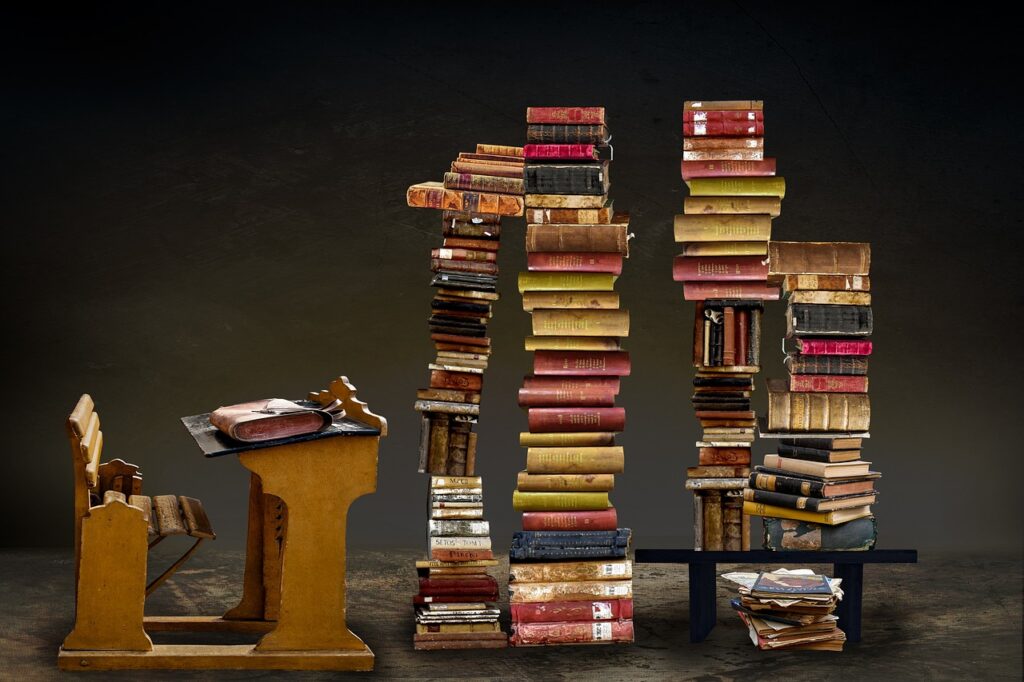学習アドバイス– category –
-

子どもがネットいじめの被害者に?親が今すぐできる7つの対処法
リンク 「うちの子は大丈夫」そう思っていませんか? スマートフォンやタブレット端末の普及により、子どもを取り巻くインターネット環境は劇的に変化しました。 便利で楽しい反面、インターネット上でのいじめ「ネットいじめ」は、深刻化する前にいち早く対応することが重要です。 見えにくいからこそ、親のあなたは子どものSOSサインに気づ... -

教員のための初任者研修:個別対応と実践の強化でステップアップ
リンク 個別対応の重要性とその方法 初任者研修がより効果的になるためには、個別対応の強化が不可欠です。 各教員の特性や勤務する学校の特徴に基づいたカスタマイズされた研修プログラムを導入することで、学びを最大化できます。 それぞれの教員が異なる背景やスキルをもっているため、一律の研修ではなく個々のニーズに合わせた内容を用... -

【子どもの学習力アップ】脳科学が明かす3つの重要ネットワークとは
近年の脳科学研究により、私たちの脳には3つの重要なネットワークが存在し、これらが学習や記憶、注意力などに大きく関わっていることが分かってきました。 これらのネットワークの働きを理解することで、お子様の学習をより効果的にサポートすることができます。 リンク デフォルトモードネットワーク(DMN):創造性を育む「お散歩モード」... -

保護者対応の新しいカタチ – 小野田正利氏の提言から学ぶ信頼関係の築き方
リンク 保護者対応の現状と課題 近年、教育現場における保護者対応の難しさが指摘されています。 モンスターペアレントという言葉が生まれて久しいものの、この表現自体が対立構造を生みかねません。 小野田正利氏は、そもそも保護者と教職員は「子どもの成長を願う仲間」であると指摘します。 対立ではなく、協力関係を築くことこそが重要な... -

子どもの未来を拓くソーシャルスキル教育
リンク ソーシャルスキル教育の重要性と本書の概要 ソーシャルスキル教育は、子どもの将来を築くための重要な要素です。 友達づきあいや集団生活での円滑なコミュニケーションは、社会人としての基盤を形成するために不可欠です。 「ソーシャルスキル教育で子どもが変わる」は、國分康孝監修のもと、小林正幸と相川充が編著した本書で、小学... -

「JAPAN GAMES」
リンク 「JAPAN GAMES」は、日本スポーツ協会が提唱する新たなスポーツイベントです。 昨年、国民スポーツ大会を皮切りに始まった3大会の統合ブランドになりますが、なぜ統合するのか? 従来の「国民体育大会」、「日本スポーツマスターズ」、および「全国スポーツ少年大会」を統合し、より多くの人々がスポーツに親しむ機会を増やすことを目... -

子どものスポーツ時の体温管理、これだけは知っておきたい基礎知識
スポーツをする子どもたちの安全を守るために、体温管理は最も重要な要素の一つです。 特に発達段階にある子どもたちは、大人と比べて体温調節機能が未熟なため、より慎重な配慮が必要です。 今回は、子どものスポーツ活動における体温管理について、基礎から実践的なアドバイスまでご紹介します。 リンク 体温管理の重要性と基本メカニズム ... -

子どもの発散的・収束的思考の育て方〜より良い問題解決者を目指そう〜
リンク 発散的思考とは 発散的思考とは、あるテーマや問題に対して多くのアイデアを出し、創造的な解決策を模索する思考のスタイルです。 この思考法は、特に芸術やデザイン、社会的な課題解決などにおいて非常に重要です。 発散的思考の特徴として、自由な発想、革新性、柔軟性が挙げられます。 例えば、子どもたちが「宇宙」のテーマで自由... -

子供への個別対応、その無力感と向き合う方法
リンク 個別対応における無力感の原因 子供への個別対応をしていると、時に無力感を感じることがあります。 例えば、登校をためらう子供の家庭訪問や、授業中に感情的になる子供への対応は、その一例です。 長年の教師としての経験をもっているにもかかわらず、関わりの少ない子供や保護者に対する個別対応の難しさを痛感しました。 特に発達... -

子どもたちの「なぜ?」を宝に!知識創造理論で探究心を育む教室づくり
「先生、なんで空は青いの?」 「どうして鳥は空を飛べるの?」 子どもたちの好奇心と探究心は、私たち大人には計り知れないパワーを秘めています。 この無限の可能性を秘めた「なぜ?」を、ただ「知る」だけで終わらせていませんか? これからの時代を生き抜くためには、子どもたちが自ら学び、考え、新しい価値を生み出す力が重要です。 そ...