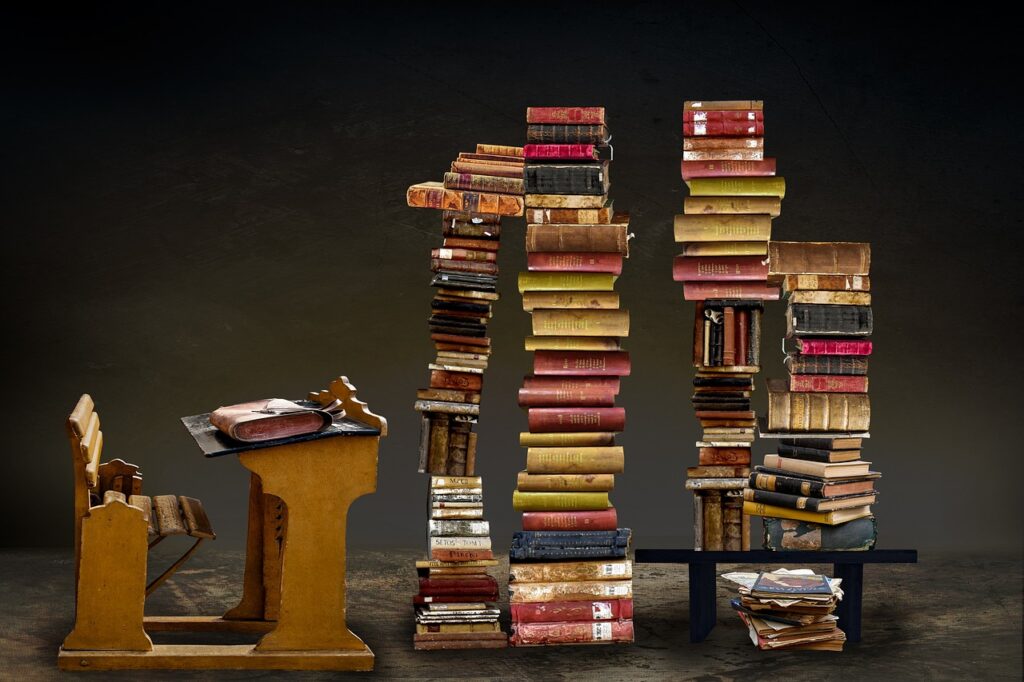学習アドバイス– category –
-

スポーツ少年団に変化の波!?親の負担軽減へ「スクール化」という選択肢
リンク 近年の共働き世帯の増加やライフスタイルの多様化に伴い、スポーツ少年団の在り方が問われています。 特に、運営の中心を担ってきた「親の会」の存在は、負担感を感じさせる要因の一つとして挙げられることも少なくありません。 そこで注目されているのが、親の会を廃止し、運営を専門コーチに任せる「スクール化」という選択です。 ... -

発達障害の過剰診断を防ぐ方法と適切なサポート「『発達障害』と間違えられる子供たち 著者 成田奈緒子氏」
リンク 増加する発達障害の診断と誤診の問題 最近、子供たちが発達障害と診断されるケースが急増しています。 特に、過去13年間でその数は約10倍に達したと言われています。 この急激な増加の背景には、誤診や過剰診断の問題が潜んでいる可能性があります。 誤診があった場合、子供たちは本来必要なサポートを受けられず、不適切な支援を受け... -

子育てを変える!山浦一保氏が提唱するコミュニケーションの秘訣
リンク イントロダクション:山浦一保氏とコミュニケーションの二軸 私たちが子どもたちの教育に携わる際、重要な要素の一つが「コミュニケーション」です。 山浦一保氏は、そのコミュニケーションにおける「黄金の二軸」を提唱し、多くの教育関係者や親御さんから支持を得ています。 コミュニケーションの黄金の二軸とは、「子どもの声をし... -

デジタル時代の子どもたちの運動不足を解消する方法
リンク 運動不足の現状とその原因 現代の社会では、技術の進歩とともに子どもの生活様式にも大きな変化が生じています。 スマートフォンやタブレット、ゲーム機など、デジタルデバイスの普及により、子どもたちは従来よりも家の中で過ごす時間が増えています。 この結果、運動不足が広がりつつあります。 具体的には、学校での運動時間や家庭... -

「学校が楽しくなる!発達が気になる子へのソーシャルスキルの教え方」レビュー:子どもの集団生活をサポートする40のアプローチ
リンク 「学校が楽しくなる!発達が気になる子へのソーシャルスキルの教え方」は、鴨下賢一氏が編著し、立石加奈子氏と中島そのみ氏が著した書籍です。 この本は、ルールを守れない、コミュニケーションが苦手な子どもたちが学校生活を楽しく過ごせるよう、臨床経験豊富な作業療法士が教える40のアプローチを紹介しています。 リンク 内容と... -

子供たちの雪遊びを安全に楽しむ方法
リンク 雪遊びに潜む危険 雪遊びは冬の楽しみの一つですが、その裏には多くの危険が潜んでいます。 たとえば、子供たちが雪玉に小石や氷を混ぜ込むことは、暴力的な結果を招く恐れがあります。 また、凍った地面で転倒しやすくなるため、怪我のリスクも高まります。 さらに、過度の興奮でかく汗が体温低下を引き起こすことも少なくありません... -

【スポーツ少年団の親御さんへ】親の会、ホントに必要?メリット・デメリットから考える理想の形
リンク スポーツ少年団における「親の会」の役割とは? スポーツ少年団は、地域の子どもたちにスポーツの楽しさを教える場であると同時に、 地域住民のボランティアによって支えられている という側面も持ち合わせています。 指導者やコーチもボランティアで活動しているケースが多く、練習場所の確保や試合の運営など、多くの業務... -

大雪で思うこと
大雪の報道を目にすると、翌日の出勤について考え始めることが多くなります。 リンク 初めての職場で働いていた際、通常は40分ほどで通勤できていましたが、大雪の影響で道路が混雑し、90分ほど掛かってしまい、少し遅刻してしまいました。 出勤すると、数名の教員が子供たちの通学路を雪かきしており、他の教員は雪かきをしたり、遅刻したり... -

「ラーケーションの日」で子どもと一緒に学びを深める!新しい学び方・休み方の魅力
リンク 「ラーケーションの日」とは? 「ラーケーションの日」は、愛知県がワーク・ライフ・バランスの充実を目指して発足させた「休み方改革」プロジェクトの一環として、2023年度に導入された新しい学び方・休み方です。 この取り組みは、子どもの学び(ラーニング)と保護者の休暇(バケーション)を組み合わせたもので、平日に学校外で体... -

「ほめる」が最強の教育ツール!京女式学校現場の「ほめほめ言葉」が子どもの心を育む【書評】
リンク 「子どもが育つ京女式学校現場のほめほめ言葉」は、長年、京女で生徒の心を育んできた吉永幸司先生による、教育現場で実践できる「ほめる」技術をまとめた一冊です。 本書では、単なるお世辞ではなく、子どもの才能や努力を具体的に褒め、自信とやる気を引き出す「京女式ほめ言葉」の数々が紹介されています。 「子どもを褒める」こと...