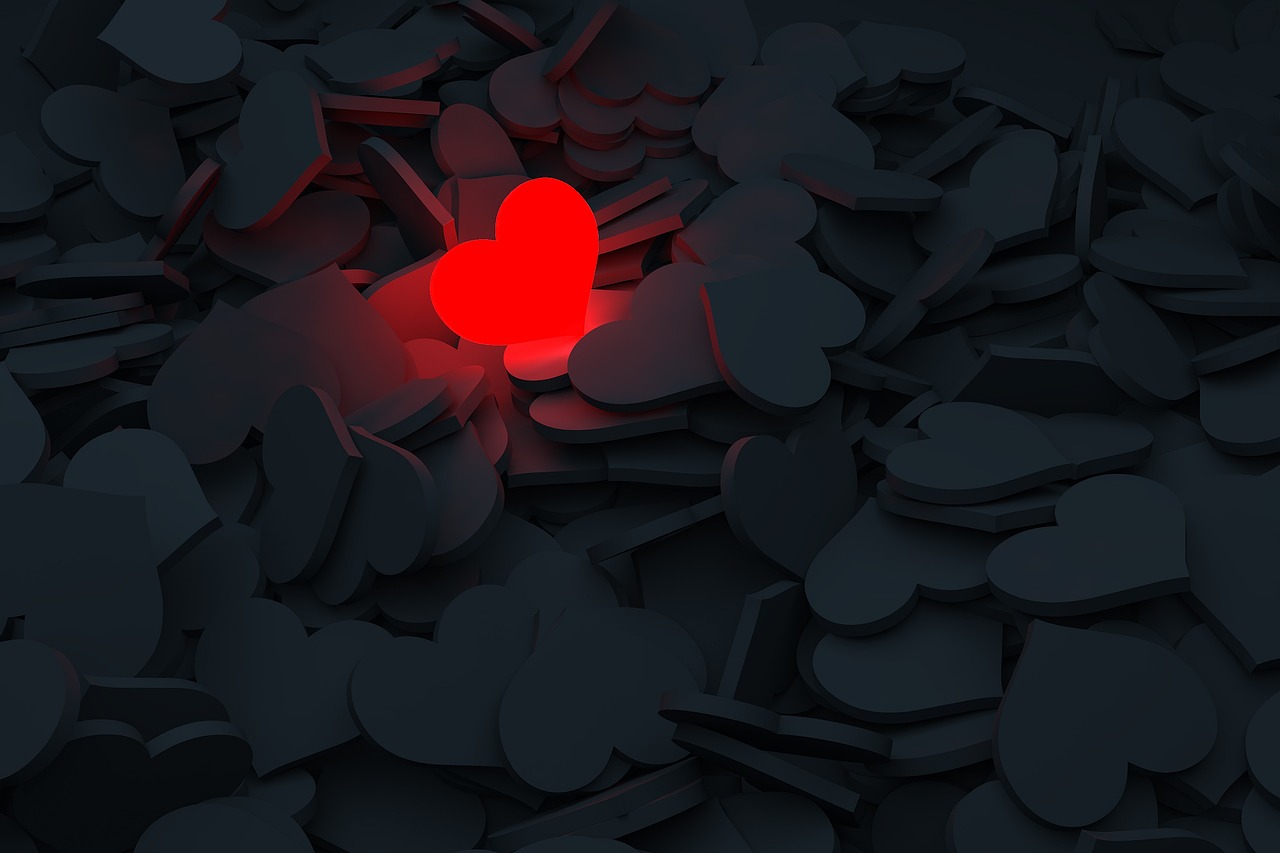「ちょっとしたことで泣いてしまう」
「怒りが爆発すると手がつけられない」
「切り替えができず、落ち込みが長引く」
子どものこうした様子に困った経験を持つ保護者や先生は少なくありません。
しかし、感情コントロールが未熟であることは、子どもの「性格のせい」ではなく、「発達の一過程」であることがほとんどです。
本記事では、感情コントロールが苦手な子どもに対する接し方のポイントを、発達心理の観点からわかりやすく解説します。対応の基本を知ることで、親も子どもも自己肯定感を損なうことなく成長していく道筋が見えてきます。
感情コントロールが苦手な理由は「脳の仕組み」にある
私たちの感情は、脳の「扁桃体(へんとうたい)」という部分で処理されます。そしてその感情にブレーキをかける役割を果たしているのが「前頭前野(ぜんとうぜんや)」という部分です。
ところが、この前頭前野は、子ども期にはまだ十分に発達していないため、自分の感情をうまく整理したり、抑えたりすることが難しいのです。
また、次のような要因も、感情コントロールの困難さを引き起こす背景となります。
- 気質的に敏感・感受性が強い
- 環境の変化にストレスを感じやすい
- 言葉で感情を表現する力が弱い
- 成功体験が少なく、自己肯定感が低い
つまり、感情を爆発させてしまうのは「わがまま」ではなく、まだ育っていない脳と、満たされない心の叫びであることを理解することが第一歩です。
子どもの「気持ち」を否定しないことが大前提
感情コントロールが苦手な子に接するとき、多くの大人は「泣かないで」「怒っちゃダメ」などと“感情を抑えようとする声かけ”をしてしまいがちです。
しかし、感情そのものは良いも悪いもありません。
重要なのは、それをどう扱うかです。
子どもが怒ったとき、泣いたときは、次のような対応を心がけましょう。
- 感情に“名前”をつける:「悔しかったんだね」「嫌だったんだね」
- 否定せず、共感で受け止める:「そう感じたんだね」「わかるよ」
- 落ち着いたあとに対話する:「あのときどうすればよかったか、一緒に考えてみよう」
このような対応は、子どもに「自分の気持ちを認めてもらえた」という安心感を与え、次に感情を整理する力を育てる土台になります。
接し方の基本:予防・共感・再学習の3ステップ
感情コントロールが苦手な子どもとの関わりで重要なのは、「その場でなんとかしよう」と焦らず、長い目で“学びのプロセス”ととらえることです。
ここでは、具体的なステップを3つに分けてご紹介します。
1. 感情爆発の“予防策”を整える
- 生活リズムを安定させる(睡眠・食事・運動)
- 予定を事前に伝える(見通しを持たせる)
- 選択肢を与える(「どっちがいい?」と選ばせる)
これらは、子どもに安心感と自己決定の経験を与え、感情の高ぶりを未然に防ぐ効果があります。
2. 感情が出たときは“共感と静観”が基本
- 感情を否定せず受け止める
- 必要に応じて、そっとそばにいる
- 暴れたり危険な行動がある場合は静かに制止
一時的な爆発に大人が動揺してしまうと、子どももますます不安定になります。
感情の波が静まるのを待つ姿勢も大切です。
3. 落ち着いたあとに“感情の再学習”を促す
- 「○○のとき、どう思ったの?」と振り返りを促す
- 「次はどう伝えられるかな?」と建設的な言葉を引き出す
- 「うまく言えたね」と小さな成功体験を積み上げる
こうしたやりとりを繰り返すことで、子どもは少しずつ「自分の感情を言葉にして、他者と関われる力」を身につけていきます。
家庭と学校での一貫した対応が効果的
感情コントロールが苦手な子どもにとって、家庭と学校での環境の一貫性は非常に大切です。
もし学校でも同様の困りごとがある場合は、以下のような情報共有が効果的です。
- 家庭で有効だった接し方(例:「怒っているときは触れずに見守る」)
- 感情のきっかけとなる場面(例:「大勢の前で急に発言を求められる」)
- 気持ちを落ち着ける方法(例:「クッションを抱えると落ち着く」)
教師との連携を図ることで、子どもにとって“どこでも安心できる居場所”を整えることができます。
まとめ:感情コントロールは「学び直せる力」。今こそ子どもと向き合うチャンス
感情の波が激しい子どもを見ると、つい「育てにくい」「難しい子」と感じてしまうかもしれません。
ですが、感情をうまく扱える力は、生きていく上で最も大切な“社会性の土台”です。
だからこそ、小さいうちに丁寧に向き合い、安心の中で学び直すことが何より重要です。
最後に、対応のポイントをまとめます。
- 感情コントロールの未熟さは脳の発達過程の一部
- 子どもの感情を否定せず、名前をつけて受け止める
- 爆発の予防、共感的対応、事後の学び直しを意識
- 家庭と学校での情報共有と一貫性を大切にする
どんなに感情的になる子どもでも、信頼できる大人との関係性の中で、感情を自分のものとして扱える力を身につけていきます。
子どもとともに、焦らず、少しずつ、一歩ずつ進んでいきましょう。
↓下記の関連カテゴリーもチェックしてみましょう。
↓下記の外部サイトもチェックしてみましょう。