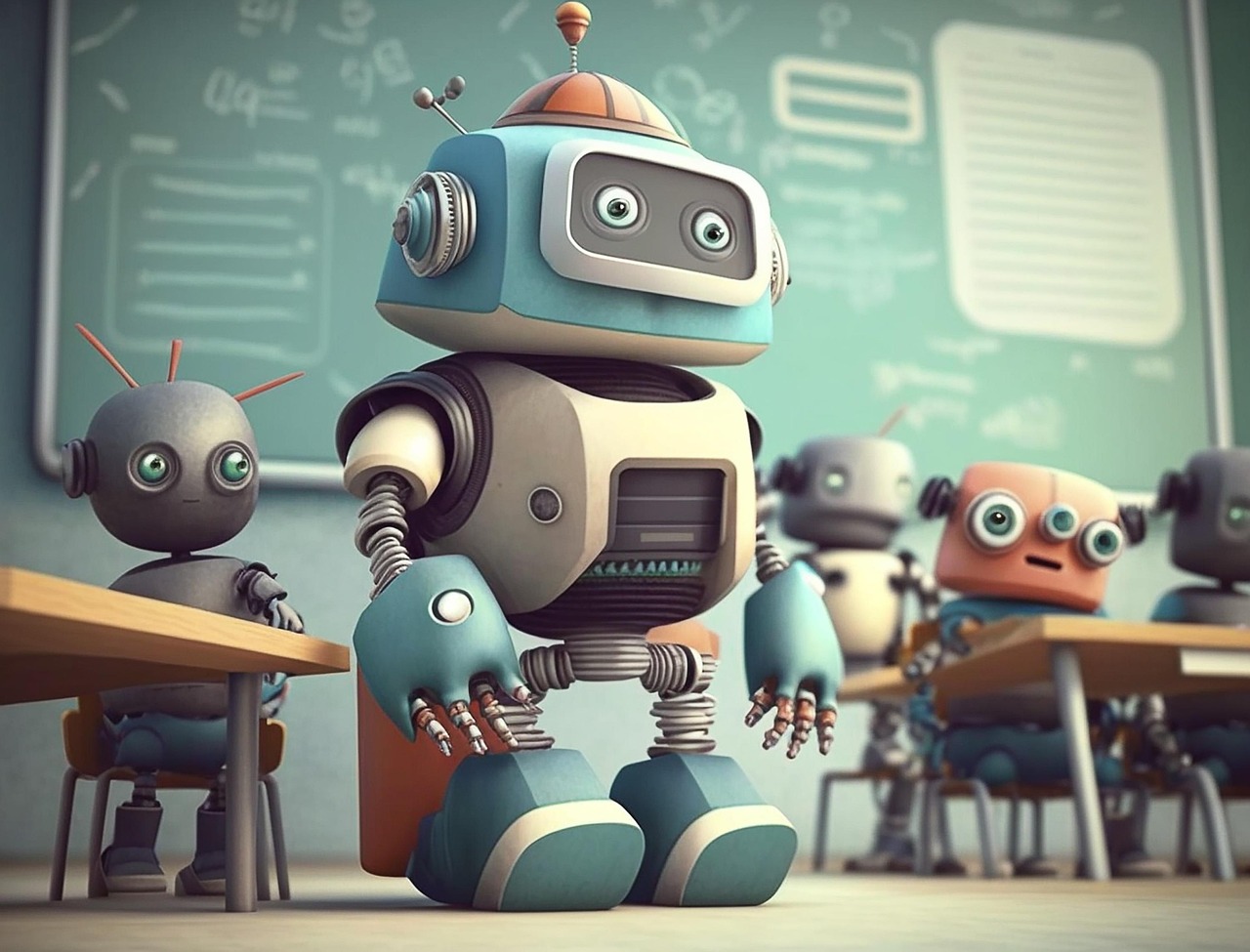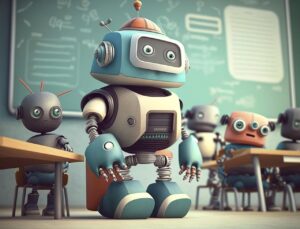「どうして学校に行きたくないの?」
「やる気がないのは甘えじゃないの?」
学校へ行くことに前向きになれない子どもを見て、そう思ってしまう保護者の方は少なくありません。
しかし、子どもが学校に行くモチベーションには、見えづらい心理的要因が深く関係しています。
この記事では、子どもの学校生活におけるモチベーションの仕組みと、それを育む家庭での接し方について、キッズ学習アドバイザーの立場から解説します。
「モチベーション」は外から与えるものではない
そもそも、「モチベーション(やる気)」は外からの命令や評価で無理やり引き出すものではありません。
心理学的に見ると、モチベーションは以下の2種類に分けられます。
- 外発的動機づけ:ご褒美や叱責など、外からの働きかけによるやる気
- 内発的動機づけ:好奇心や達成感など、自分の内側から湧き出るやる気
子どもにとって、学校へ行くモチベーションを長続きさせるカギは「内発的動機づけ」です。
つまり、「行かなければならないから」ではなく、「行きたい」「面白い」「自分に意味がある」と感じられるかどうかが重要なのです。
子どもが学校に行きたくなる3つの心理的要素
では、どんなときに子どもは学校へ行きたいと思えるのでしょうか?
学習動機や行動理論の研究から、以下の3つが特に大切とされています。
1. 「自分で選べている」という実感(自己決定感)
人は、自分の意思で行動していると感じられるとき、最も意欲的に動けます。
逆に、「やらされている」「強制されている」と感じると、モチベーションは低下します。
子どもも同じで、「自分が学校に行くと決めた」「今の目標は自分のものだ」と感じられる環境が、継続的な意欲につながります。
2. 「自分にもできる」という手応え(有能感)
できなかったことが少しずつできるようになる体験は、子どもの心を強く支えます。
宿題が終わった、発表ができた、先生に褒められた——
こうした小さな成功の積み重ねが、「自分にもできるんだ」という自信に変わっていきます。
つまり、「できた」という感覚が子どもの行動を前向きにする源になるのです。
3. 「ここにいていい」という安心感(関係性の安心)
どんなに学力が高くても、人間関係で居場所を感じられないと、学校は苦痛な場になります。
- 友だちがいる
- 先生に認められている
- 自分の話を聞いてくれる人がいる
こうした関係性の中で、「自分はここにいていい」と感じられることが、子どもの心の土台となります。
保護者ができるモチベーションサポートの実践例
子どもが学校へ行きたくなるために、家庭でできる具体的なサポート方法をいくつか紹介します。
「学校=学びだけではない」視点を持つ
学校は学力をつける場であると同時に、人間関係・生活スキル・社会性を育てる場所でもあります。
「勉強だけが目的じゃない。いろんな人と関わる中で、自分の可能性を広げていけるよ」と伝えることで、学校へのイメージを柔らかく前向きなものに変えていくことができます。
子どもの声をしっかり受け止める
「行きたくない」という言葉の背景には、不安、恐怖、疲労、未解決のトラブルなど様々な感情が隠れています。
その声を「ダメだ」と否定するのではなく、
- 「そう思うんだね」
- 「何があったか、教えてくれる?」
- 「それはつらかったね」
と共感しながら受け止めることが、安心感と信頼の土台になります。
モチベーションが湧かないときは「小さな目的」を一緒に見つける
モチベーションはゼロからいきなりフルスロットルにはなりません。
まずは、小さな「行く理由」を一緒に考えてみましょう。
- 「今日は図工があるよね。楽しみにしてたんじゃない?」
- 「友だちに借りた本、返しに行く日だよね」
- 「昨日頑張ったプリント、先生に見せたいね」
些細なきっかけを糸口にすることで、心のハードルが少しずつ下がっていきます。
「やる気が出るのを待つ」のではなく、「動いてからやる気を育てる」
脳科学的にも、やる気は「行動の後」に生まれることが多いとされています。
つまり、「やる気が出たら行く」ではなく、「少し行ってみたらやる気が湧いた」という順番なのです。
「今日は1時間だけ行ってみよう」
「校門まで一緒に行ってみよう」
といった小さな一歩が、モチベーション再起動のきっかけになることがあります。
学校へ行くことを「目的」ではなく「手段」にする
本来、学校へ行くことはゴールではなく、「学び」「成長」「出会い」の手段であるはずです。
「学校へ行くこと」だけを目的にしてしまうと、行けなかった日には自分を責めてしまいがちになります。
ですが、「自分の未来のために、少しでも前進する」という視点をもてば、不登校や登校しぶりの子も、自分なりのペースで歩み出すきっかけがつかめます。
まとめ:子どもの「行きたい気持ち」を信じ、育てていく
子どもには本来、知りたい・関わりたい・認められたいという強い内発的動機があります。
それが一時的に見えなくなっているときこそ、周囲の大人の接し方が大きな影響を与えます。
子どもが学校へ向かうのは、「評価されるため」でも「義務だから」でもなく、
「自分らしく生きるための土台をつくる場所」であること。
そうした視点を大人も持ち続けながら、子どものペースに寄り添うことが、モチベーションを育てる最大の支援となります。
↓下記の関連カテゴリーもチェックしてみましょう。
↓下記の外部サイトもチェックしてみましょう。