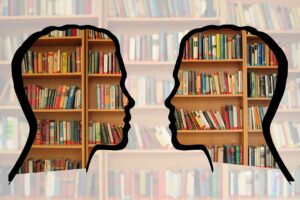「グループディスカッションを取り入れたいけど、子どもたちがちゃんと話し合えるか不安…。」
そう思っていませんか?
この記事では、小学校のグループディスカッションを成功に導くための具体的な方法を5つのステップでご紹介します。
この記事を読めば、子どもたちの「考える力」と「伝える力」を育み、活気あふれる授業を実現できます。
ぜひ最後まで読んで、明日からの授業に役立ててください!
グループディスカッションのメリット
グループディスカッションは、従来の一斉授業では得られない多くのメリットを子どもたちにもたらします。
主なメリット
- 多様な意見に触れ、視野が広がる:自分とは異なる考え方や価値観に触れることで、多様性を認め、柔軟な思考力を育むことができます。
- コミュニケーション能力が向上する:自分の意見を伝え、相手の意見を聞くことを繰り返す中で、自然とコミュニケーション能力が身につきます。
- 主体性や協調性を育む:グループで協力して課題に取り組む経験を通して、主体性や責任感、協調性を育むことができます。
- 思考力・表現力を高める:自分の考えを整理し、論理的に説明したり、相手の意見に対して質問したりする中で、思考力や表現力が磨かれます。
- 学習意欲の向上:受け身ではなく、主体的に学習に参加することで、学習意欲の向上に繋がります。
グループディスカッションは、子どもたちの社会性やコミュニケーション能力を育むだけでなく、21世紀型スキルとも呼ばれる、これからの社会を生き抜くために必要な力を育む有効な学習方法です。
グループディスカッション導入の準備
グループディスカッションをスムーズに進めるために、事前準備が重要です。
1. テーマ設定
子どもたちの興味関心を引く、年齢や発達段階に合わせたテーマを選びましょう。
- 身近な生活と関連付ける: 学校生活、家庭生活、地域社会など、子どもたちにとって身近なテーマを選ぶと、活発な意見交換が期待できます。
- 複数の意見が出やすいテーマにする: はい/いいえで答えられない、多様な意見が出やすいテーマを設定することで、議論が深まります。
- 子どもたちの意見を参考に: 事前にアンケートや話し合いを行い、子どもたちの意見をテーマ設定に反映することで、学習意欲を高めることができます。
2. グループ編成
グループの人数やメンバー構成は、学習目標や子どもたちの状況に合わせて検討しましょう。
- 4~5人程度のグループ: 多様な意見が出やすく、かつ全員が発言しやすい人数構成です。
- 学習能力や性格を考慮: 話し好き、おとなしいなど、子どもたちの特性を考慮してグループを編成することで、偏りをなくし、全員が参加しやすい雰囲気を作ることができます。
- 役割分担を明確にする: 司会、書記、発表者など、役割分担を明確にすることで、スムーズな議論を進めることができます。
3. 環境設定
円になりやすく机を配置する、グループワーク用のホワイトボードを用意するなど、話し合いやすい環境を整えましょう。
グループディスカッションを活性化させるためのコツ
せっかくグループディスカッションを取り入れても、子どもたちが積極的に参加しなければ意味がありません。
ここでは、子どもたちの発言を引き出し、活発な議論を生み出すためのコツをご紹介します。
1. 発言しやすい雰囲気作り
- 意見を否定しない: 間違えを恐れて発言しづらくなってしまわないよう、「どんな意見も素晴らしい」という雰囲気作りが大切です。
- 「いいね!」「おもしろいね!」など、ポジティブな言葉かけ: 肯定的な言葉をかけることで、子どもたちの発言意欲を高めることができます。
- 視覚的なサポート: 図やイラスト、キーワードなどを用いることで、思考を整理しやすく、発言しやすくなります。
2. 思考を深めるための質問
- 「なぜそう思ったの?」「他に意見はあるかな?」: 子どもの意見を引き出し、深く考えさせる問いかけを意識しましょう。
- 具体的な事例を挙げる: 抽象的な話ではなく、子どもたちにとって身近な具体的な事例を挙げることで、イメージしやすく、議論が活発になります。
- 「もし~だったらどうなるだろう?」: 思考実験を取り入れることで、想像力を掻き立て、多様な意見を引き出すことができます。
3. 全員参加型の工夫
- 発言カード: 事前にテーマに関するキーワードや質問を記入したカードを配ることで、発言のきっかけ作りになります。
- Think-Pair-Share: まず個人で考え、次にペアで意見交換、最後にグループで共有する、段階を踏んだ手法も有効です。
- 役割分担: 司会、書記、発表者、時間管理など、役割を分担することで、責任感を持って参加することができます。
グループディスカッション後の振り返り
グループディスカッション後には、単に結論を出すだけでなく、以下のポイントを踏まえて振り返りをしましょう。
1. 議論の過程を振り返る
- 「どんな意見が出たかな?」: グループごとに、どんな意見が出たか発表させ、全体で共有しましょう。
- 「なぜその結論に至ったのか?」: 結論に至るまでのプロセスを振り返ることで、思考の道筋を明確にできます。
2. 学びを深める
- 「新しい発見はあった?」: 他のグループの意見を聞くことで、新たな視点を得たり、自分の意見を深めたりすることができます。
- 「他の意見と自分の意見の違いは何だろう?」: 異なる意見を比較することで、多様な価値観への理解を深めることができます。
3. 次回への改善点
- 「もっとよくするために、次はどうしたらいいかな?」: グループディスカッションの方法や内容について、子どもたち自身に振り返らせることで、主体的学習を促進します。
グループディスカッションで子どもたちの可能性を広げよう!
グループディスカッションは、子どもたちの「考える力」「伝える力」「協力する力」など、未来を生き抜くために必要な力を育む有効な学習方法です。
最初は戸惑う子どもたちもいるかもしれませんが、今回ご紹介したポイントを参考に、段階的に取り入れていくことで、子どもたちは積極的に議論に参加し、自ら学びを深めていくでしょう。
ぜひ、グループディスカッションを通して、子どもたちの可能性を広げ、活気あふれる授業を実現してください!