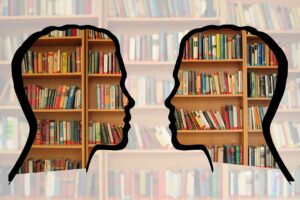「うちの子、もっとできるはずなのに…」
そう感じながらも、どうすればいいのか分からず、悩んでいませんか?
子どもは皆、無限の可能性を秘めています。しかし、多くの子どもたちは、自分自身の能力に気づかないまま、あるいは、どうすれば能力を伸ばせるのか分からずに、「無意識の壁」に阻まれ、本来の可能性を発揮できないでいることがあります。
この記事では、そんな「無意識の壁」を突破し、お子さんの秘めた才能を最大限に引き出すためのヒントをお伝えします。
具体的には、学習心理学の観点から「無意識的無能」「意識的無能」「意識的有能」という3つの段階を解説し、それぞれの段階に応じた効果的な学習方法をご紹介します。
この記事を読むことで、あなたは以下の3つの恩恵を得られます。
- お子さんの現在の学習段階を客観的に把握できるようになります。
- 各段階に応じた効果的な学習方法を理解し、実践できるようになります。
- お子さんの隠れた才能を発見し、可能性を広げるための具体的な方法を学び、自信を持ってサポートできるようになります。
才能は眠っているだけ!「無意識的無能」な状態とは?
「無意識的無能」とは、簡単に言うと「自分が何ができないのかすら気づいていない状態」のことです。
例えば、自転車に乗れない子どもは、自転車に乗ることの難しさや、バランス感覚を養うことの重要性を認識していません。
この段階では、子ども自身が「できるようになりたい!」という意欲や好奇心を抱くことが非常に重要です。
無意識的無能な子どもへの学習サポート
- 楽しい!面白い!を最優先に: まずは、子ども自身が「やってみたい!」「もっと知りたい!」と思えるような、楽しい経験を通して学習意欲を高めることが重要です。
- 成功体験を積み重ねる: 簡単な課題やゲームなどを通して、小さな成功体験を積み重ねることで、「やればできる!」という自信を育みます。
- 興味関心を広げる: 様々なことに触れさせ、興味関心の幅を広げることで、新たな才能を発見するきっかけを与えましょう。
「できない!」に気づき始めた時が成長のチャンス!「意識的無能」な状態とは?
「意識的無能」とは、「自分はこれができない」と認識している状態です。
先ほどの自転車の例で言えば、練習する中で「自分はバランスを取るのが苦手だ」と感じる段階です。
この段階では、子どもは「できるようになりたい!」という気持ちと、「でも、難しい…」という フラストレーションを同時に抱えがちです。
意識的無能な子どもへの学習サポート
- 具体的な目標設定とスモールステップ: 大きな目標を達成するために、小さなステップに分解し、一つずつクリアしていくことで、達成感を味わいやすくします。
- 効果的な学習方法の導入: 得意な学習方法、苦手な学習方法があるように、子どもによって最適な学習方法は異なります。視覚情報に強い、聴覚情報に強いなど、子どもの特性に合わせた学習方法を取り入れることが重要です。
- 忍耐強く寄り添う姿勢: できないことに対するフラストレーションや焦りを感じやすい時期なので、「大丈夫、ゆっくり練習していこうね」と、根気強く寄り添うことが重要です。
「できた!」の喜びを自信に!「意識的有能」な状態を目指そう!
「意識的有能」とは、「練習すればできるようになった!」という状態です。
自転車の例で言えば、何度も練習し、転びながらも、最終的にはスムーズに自転車に乗れるようになった状態です。
この段階では、「できた!」という喜びや達成感を味わうことで、自己肯定感や自己効力感を育むことができます。
意識的有能な子どもへの学習サポート
- 更なる目標設定: 一度できるようになったことでも、さらに上のレベルを目指したり、応用問題に挑戦したりすることで、学習意欲を維持します。
- 他の学習への応用: 習得したスキルや知識を、他の学習や日常生活の中で活用することで、学習の楽しさを実感させます。
- 自立した学習習慣の育成: 自分で計画を立て、実行し、評価できるようになることで、生涯にわたって学習を続けることができるように導きましょう。
「無意識の壁」を超えて、未来を拓く!
子どもたちの可能性は無限大です。
しかし、「無意識の壁」に阻まれ、その才能を眠らせてしまっている可能性もあります。
この記事でご紹介した内容を参考に、お子さんの学習段階に合わせた適切なサポートをすることで、「無意識の壁」を突破し、お子さんの秘めた才能を最大限に引き出しましょう!
そして、子どもたちが自信に満ち溢れ、自身の力で未来を創造していく姿を、私たち親は温かく見守り、応援していきましょう。