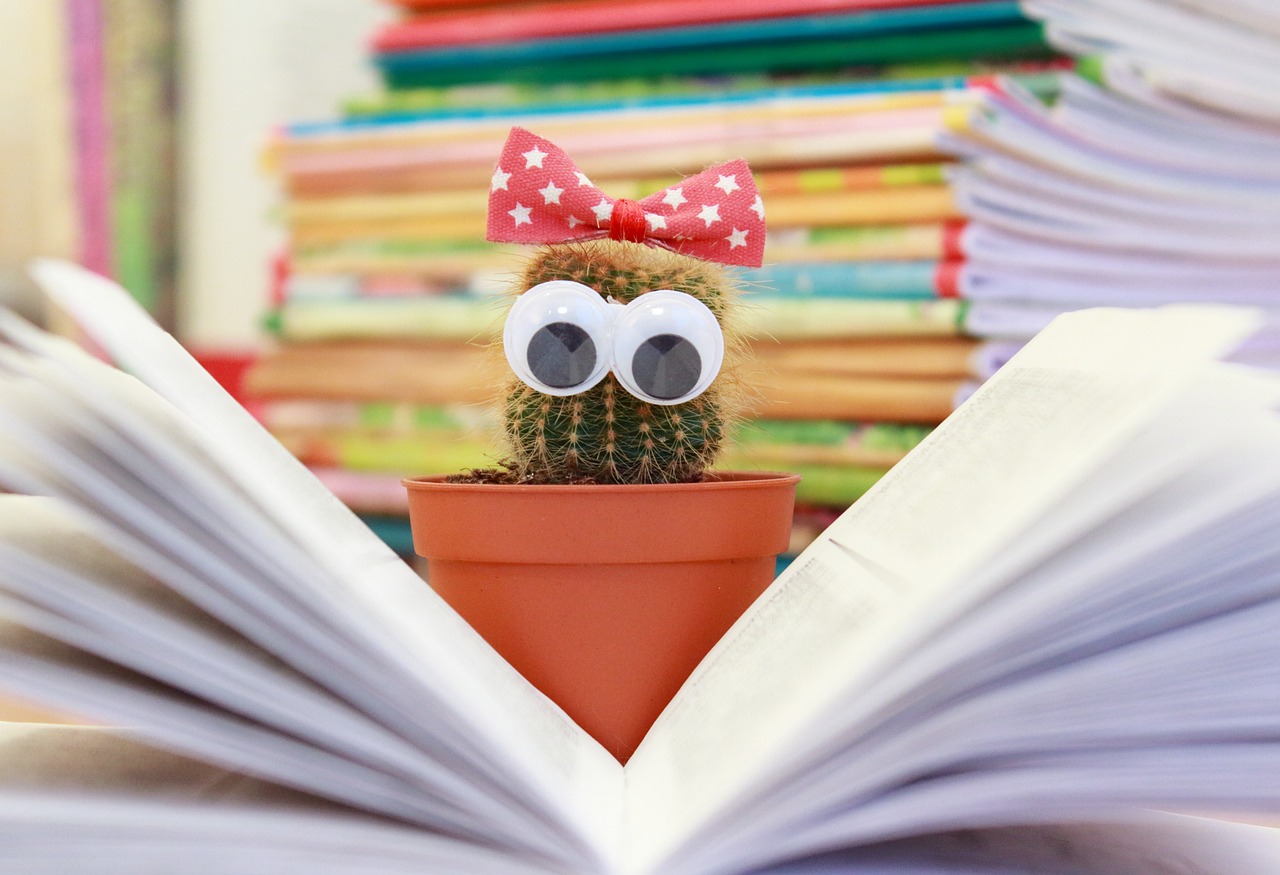「うちの子、なかなか集中力が続かなくて…」
「もっと学習意欲を高めてあげたいけど、どうすればいいか分からない…」
子育てをしていると、このような悩みを抱えることは少なくありませんよね。特に、子どもの学習面は、将来にも大きく関わることなので、不安を感じやすい部分でしょう。
そこで今回は、子どもの可能性を最大限に引き出すために重要な「発達の最近接領域」という概念と、それを活かした適切なサポート方法について解説していきます。
「発達の最近接領域」って?
「発達の最近接領域」とは、ロシアの心理学者 レフ・ヴィゴツキーが提唱した概念で、「子どもが一人でできること」と「大人や能力の高い人と一緒にできること」の間に存在する領域のことを指します。
例えば、4歳の子供が一人でパズルを完成させることが難しいとしても、親が隣でヒントを出したり、ピースを一緒に探したりすることで完成させることができるかもしれません。
この「一人でできないけれど、大人のサポートがあればできる」という領域こそが、「発達の最近接領域」にあたります。
子どもの「発達の最近接領域」の見つけ方
子どもの「発達の最近接領域」を見つけるためには、まずお子さまをよく観察することが大切です。
- どんなことに興味や関心を持っているのか?
- 何が得意で、何が苦手なのか?
- どんなことに挑戦したがっているのか?
日常生活の中で、お子さまの様子をよく観察し、メモを取ってみるのも良いでしょう。
年齢別に見る「発達の最近接領域」の例
- 2歳児: 一人で靴を履くことは難しいが、親が「右足から履こうね」などと声かけをすることで履けるようになる
- 4歳児: 一人でひらがなを書くことは難しいが、親が一緒に練習したり、見本を見せることで書けるようになる
- 6歳児: 一人で自転車に乗ることは難しいが、補助輪を外して練習したり、親が後ろから支えてあげることで乗れるようになる
このように、「発達の最近接領域」は、子どもの年齢や発達段階によって異なってきます。
大切なのは、「できない」に注目するのではなく、「あと少しでできるようになりそう」な部分を見つけることです。
発達の最近接領域を活かしたサポート方法
子どもの「発達の最近接領域」を理解したら、次はそれを活かしたサポートをしていくことが重要です。
具体的なサポート方法の例
- ヒントを与える: 問題を解決するためのヒントを与え、子ども自身で考え、行動できるように促す
- 一緒に取り組む: 難しい課題に挑戦する際には、親や先生が一緒に取り組み、成功体験を共有する
- 段階的に目標を設定する: 最初から難しい目標を設定するのではなく、達成可能な小さな目標を段階的に設定することで、モチベーションを維持する
過度な援助や指示は逆効果!
ただし、注意すべき点は、過度な援助や指示は子どもの自主性を損ない、学習意欲を低下させる可能性があるということです。
あくまでも、子ども自身が主体的に課題に取り組み、解決できるようなサポートを心がけましょう。
まとめ|子どもの可能性を広げる「発達の最近接領域」
「発達の最近接領域」を理解し、適切なサポートを行うことは、子どもの能力を最大限に引き出し、学習意欲を高めるために非常に重要です。
ぜひ、今日からお子さまの「できる」を見つけて、適切なサポートを実践してみてください。
子どもの学習に関するお悩みは、専門家にご相談ください!
私たち学習アドバイザーは、「発達の最近接領域」を踏まえた、お子さま一人ひとりに最適な学習プランをご提案しています。
子どもの学習にお悩みの方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。