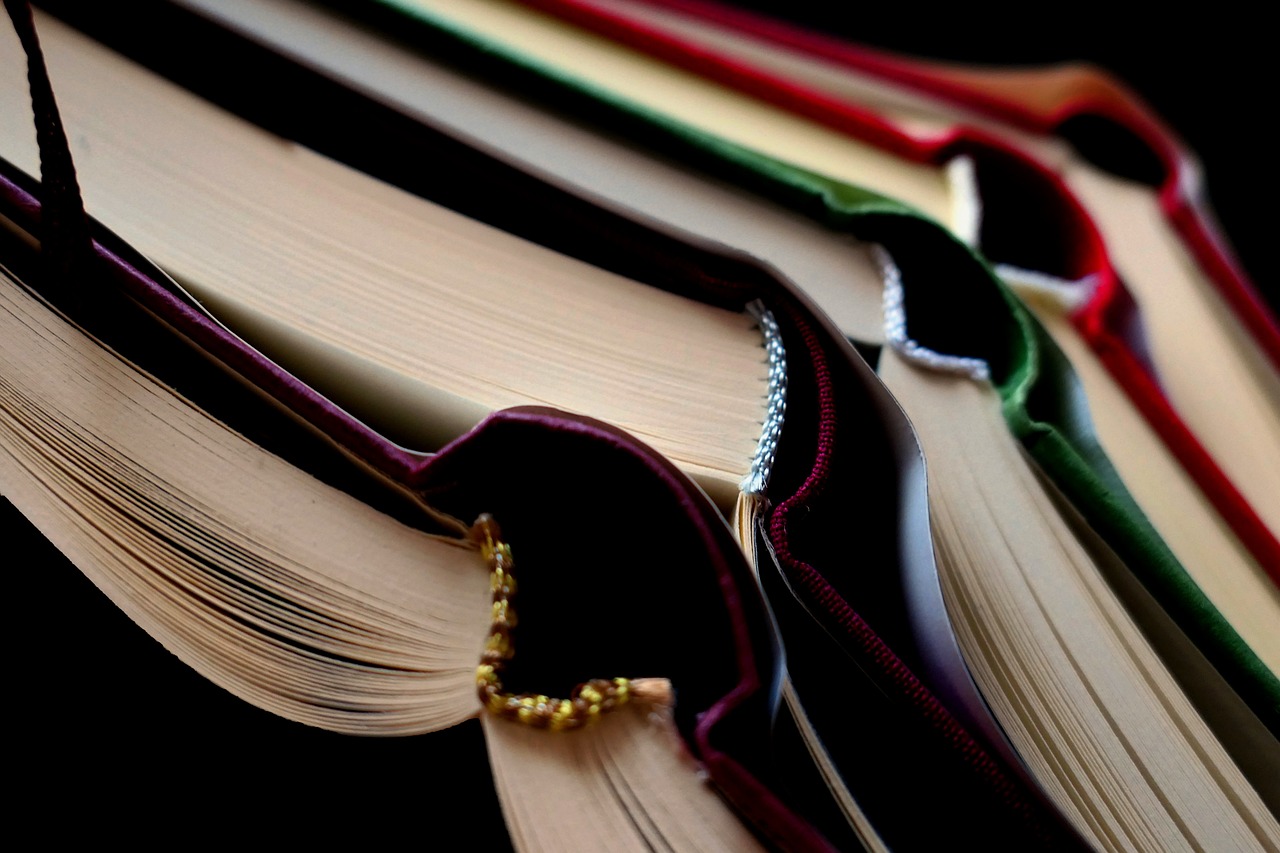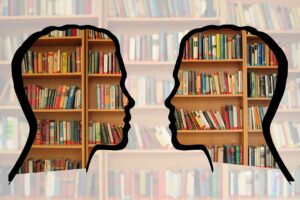なぜ「文学」と「説明文」の読み方を学ぶ必要があるのか?
現代社会において、情報を読み解く力は必要不可欠です。
日々触れる膨大な情報の中から、必要な情報を正しく理解し、自分の考えをもつことが求められます。
この「読み解く力」の基礎を育むのが、国語教育です。
特に、小学校で学ぶ「文学」と「説明文」は、それぞれ異なる読み方を学ぶことで、多角的な視点や論理的思考を養うことができます。
「文学」は、登場人物の心情や情景描写を正しく読み解くことで、想像力や共感力を育みます。
一方、「説明文」は、筆者の主張や論理展開を正しく読むことで、分析力や批判的思考力を養います。
本記事では、開智国際大学紀要に掲載された遠藤真司先生の論文を参考に、「文学」と「説明文」の効果的な読み方を解説していきます。
教材の読み方の多様性
「ごんは死んだのか」という質問は、教材の読み方の多様性を示す良い例です。
教科書に「死んだ」という記述がないため、子どもたちは「ごんは死んだのか、それとも生きているのか」と議論します。
このような議論は、教材が子どもに与える影響を考える上で重要です。
教材は単なる知識の伝達ではなく、子どもの考え方や表現力を育てるツールとして機能します。
文学作品と説明文の違い
教材の正しい読み方は、子どもの学習や発達に大きな影響を与えます。
文学や説明文の正しい読み方を通じて、子どもたちは新しい視点や考え方を学びます。
文学を読む際には、登場人物の心情や背景、作者の意図などを想像しながら、作品の世界に没頭することが大切です。
説明文を読む際には、文章の構成や情報の流れを理解し、論理的に思考することが重要です。
小学校国語教材の読み方を理解することは、子どもたちの読書力向上に大きく役立ちます。
文学では想像力を、説明文では論理的な思考力を育むことができます。
まとめ
遠藤真司氏の論文「小学校国語科教材の読み方 ~文学と説明文の違いから~」は、教材の正しい読み方が子どもの学習や発達に与える影響を考察しています。
文学と説明文の違いを理解し、教材の多様性を活かすことで、子どもたちは新しい視点や考え方を学びます。
現職教員はこの文種の違いを理解し、その読み方の違いを明確に区別した上で子どもたちの読書活動をサポートし、豊かな学びを得られるように支援していくことが重要です。