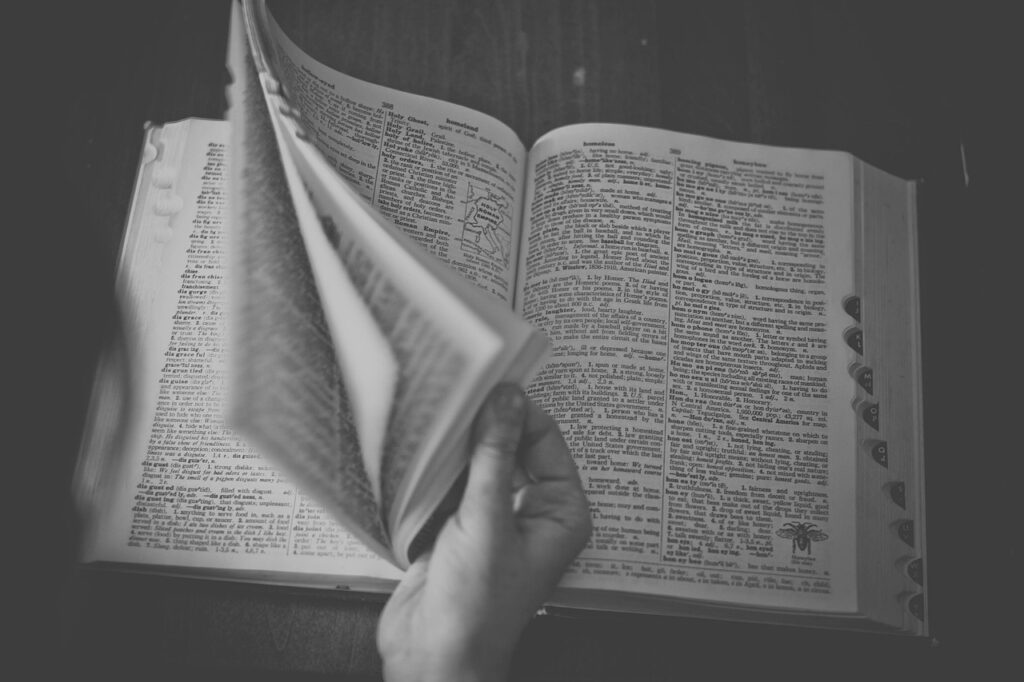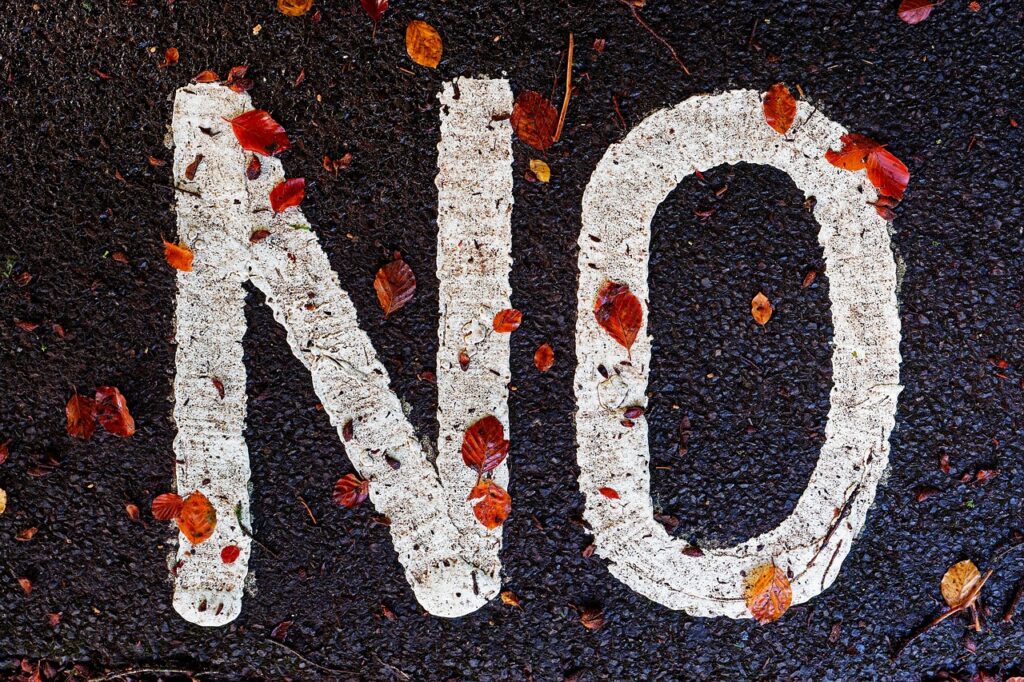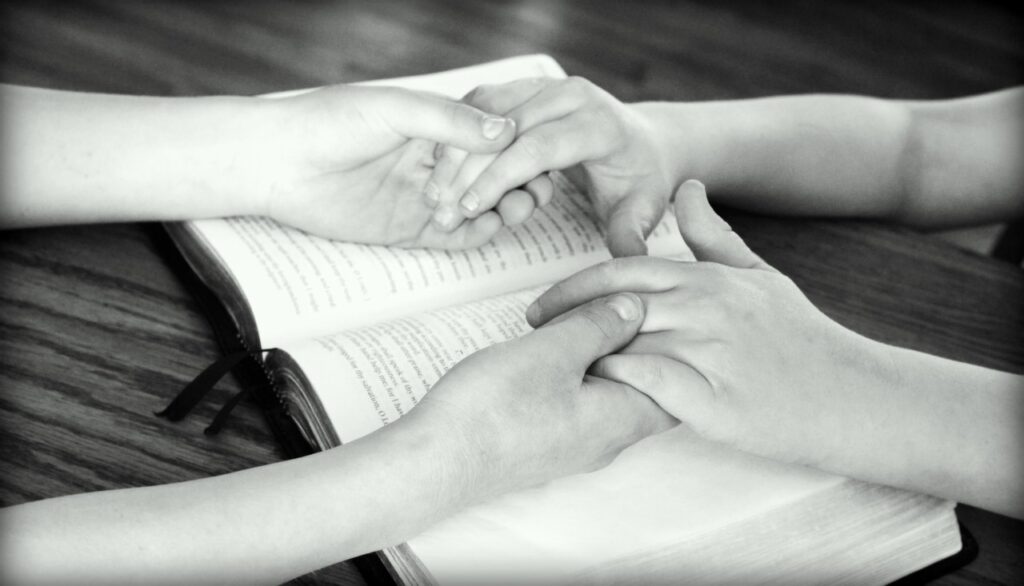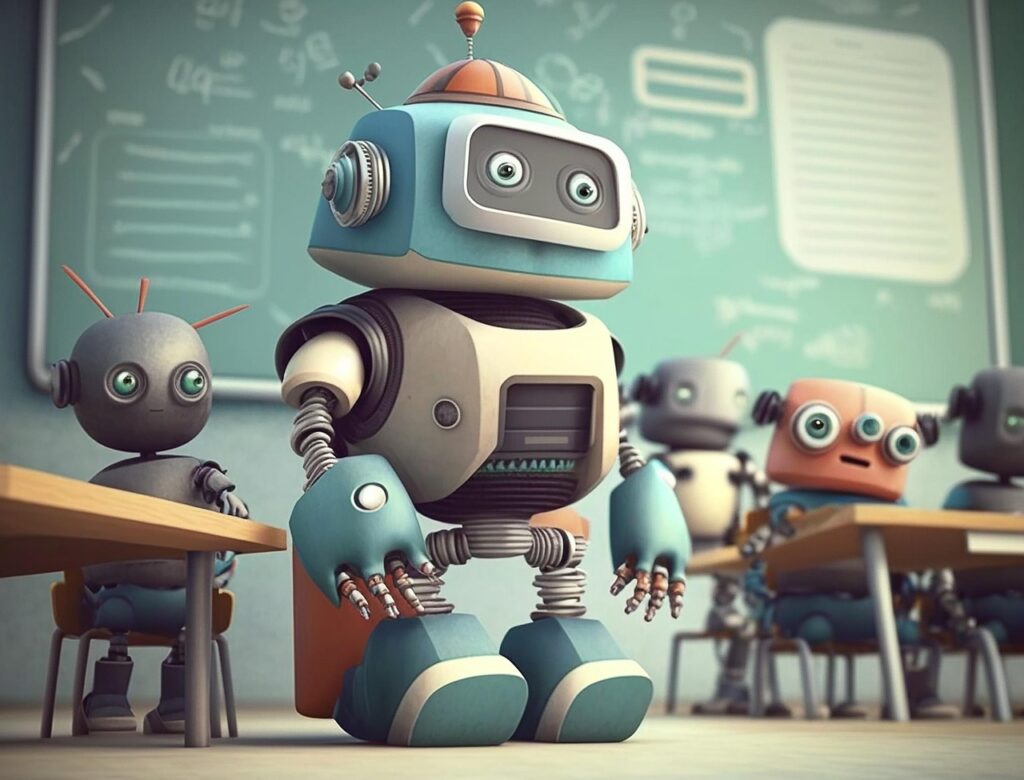ブログ記事
-

なぜ「頑張ったね」だけでは足りないのか?──努力信仰の落とし穴と子どもに必要な声かけとは
「頑張ってえらいね」「もっと頑張ろう」──日々、子どもへの声かけとしてよく使われる言葉です。もちろん、努力することの大切さを伝えるのは教育の本質でもあります。 しかし一方で、「頑張ることだけを肯定」する声かけが、子どもの心を知らず知らずに追い詰めることもあるのです。 この記事では、「努力至上主義」のリスクと、子どもの心... -

「聴く力」は育てられる──受動的な聴き方と能動的な聴き方の違いとは
「ちゃんと話を聞いてるのに、なんだか通じない」「子どもが私の話をまったく聞いていない気がする」 家庭や教育現場でこんな経験をしたことはありませんか? それは、単に「聞いている」つもりでも、本当に“聴けている”わけではないからかもしれません。人の話を聴くには、「受動的な聴き方」と「能動的な聴き方」の2つがあります。 本記事... -

子どものボキャブラリーを豊かにするには?今すぐできる5つの習慣
言葉は思考の器――。 この言葉が示すように、子どもが物事を理解し、考え、表現していくうえで、「語彙(ボキャブラリー)」の豊かさは欠かせない力です。語彙力が高い子は、自分の気持ちを整理しやすく、他者との意思疎通もうまくいきます。 逆に、語彙が不足すると「わかっているのに言えない」「思いが伝わらない」といったコミュニケーシ... -

子どもの登校しぶり:保護者と担任の考えが違うとき、どう向き合えばいいか?
子どもが学校に行きたがらない――。 その時、保護者としては「無理に行かせるより、まずは心のケアを優先したい」と思う一方で、学級担任からは「出席し続けることでリズムが整うから、休ませない方がいい」との意見が寄せられることがあります。 子どもを想う気持ちは同じはずなのに、保護者と担任とのあいだに温度差があると、かえって悩み... -

夏休み明け、子どもの「心のエンジン」がかからない?見落とされがちなメンタルヘルスのサインと対処法
夏休みが終わると同時に、子どもの表情が曇りがちになる。登校前になると「お腹が痛い」「頭が痛い」「行きたくない」とつぶやく。そんな姿に、戸惑いや心配を抱える保護者の方も多いのではないでしょうか? 実は、夏休み明けは子どものメンタルが揺れやすい「心の節目」です。本記事では、夏休み明けに起こりやすいメンタル不調の背景と、家... -

子どもの登校しぶり、夫婦で意見が食い違ったらどうする?
子どもが学校に行きたがらない。朝になるとお腹が痛い、頭が痛い、泣き出してしまう。そんな登校しぶりに直面したとき、夫婦の間で対応の考え方が異なることはよくあります。 「甘やかしちゃダメだ、無理にでも行かせるべき」という夫と、「無理はさせたくない、少し休ませて様子を見たい」という妻。あるいはその逆かもしれません。 実はこ... -

子どもの夏休み明けがスムーズになる!親が気をつけたい5つの視点
長い夏休みが終わり、いよいよ新学期。子どもたちにとっては、心も体も生活リズムも大きく切り替わるタイミングです。 実は、この「夏休み明け」は、子どもの心が不安定になりやすい時期。 この記事では、キッズ学習アドバイザーの視点から、夏休み明けに向けて保護者が注意すべきポイントを5つの視点から解説します。 親の「先回りの不安」... -

夏の終わり、「行きたくない」のサインにどう向き合うか
夏休みも終盤。カレンダーが8月後半になると、保護者の方から「子どもが『学校行きたくない』と言い出しました」と相談を受けることが少なくありません。 長期休暇明けに見られる登校しぶりや拒否には、単なる「サボりたい」以上の理由が隠れていることが多くあります。 この時期に親ができることは、「無理に登校を促すこと」ではなく、子ど... -

「相手は自分と違う」──その気づきが子どもの心を育てる
「なんであの子はそうするの?」「わたしなら絶対にしないのに」。そんな言葉が子どもから聞こえてきたら、それは社会性の成長が始まっているサインかもしれません。 子どもたちは成長の過程で、「自分と相手は違う存在である」という事実に何度も直面します。この気づきこそが、思いやり・共感・協調性といった人間関係の土台を築く第一歩で... -

魅力的なフィジカルリテラシーの世界へようこそ!子どもの成功の鍵を握る力を育むために
フィジカルリテラシーという言葉を聞いたことがありますか?現代の教育において、見逃せない大切なコンセプトです。 本記事では、フィジカルリテラシーが子どもの成長にどのように役立つか、具体的な方法とともに詳しく解説します。この記事を読むことで、あなたのお子さんが今後どのように成長し、成功していくのかのビジョンが広がることで... -

言葉にしない「伝え方」──非言語コミュニケーションで気をつけたいこと
言葉にしなくても、私たちは多くを伝え合っています。まなざし、身振り、声のトーン、距離感……それらすべてが非言語コミュニケーションです。 特に子どもとの関わりでは、大人の表情や態度、ちょっとした“間”が子どもに強い印象を与えることがあります。 本記事では、非言語コミュニケーションにおける注意点について、心理学的な視点を交え... -

子どもの所作に“品”を──TPOに合ったふるまいを育てるには
「うちの子、場所や相手に合わせた態度ができなくて…」「急に大声を出したり、場にそぐわない動きが気になります」 このような相談は、学齢期の保護者からよく寄せられます。子どもにとって「TPOにあった所作」は、社会の中で信頼され、スムーズに関係を築くための基本的な力です。 本記事では、子どもの発達に応じたTPOの捉え方と、日常生活... -

「相手を尊重する」──子どもの人間関係を育てる土台
「ちゃんと友だちと仲良くしてね」「人の気持ちを考えて行動しようね」 保護者や先生が日々、子どもたちに伝えるこの言葉。でも、その“本当の意味”を、子どもたちはどれくらい理解しているでしょうか? 子どもにとって「相手を尊重する」とは、単なるマナーや礼儀の話ではありません。それは、自分と違う他者の存在を肯定しながら、安心して... -

不安の防衛:心を守るためのメカニズムの理解
不安は、誰もが経験する自然な感情の一つですが、過剰な不安は日常生活に支障をきたすことがあります。こうした不安に対処するために、人は無意識のうちにさまざまな心理的防衛メカニズムを活用します。 これらの防衛は一時的に心を守る役割を果たしますが、その効果や持続性は個々の状況により異なります。ここでは、不安に対する一般的な防... -

子どもに響く言葉とは?──声かけの質が育てる「自信」と「安心」
「頑張ってるね」と言ったのに、子どもの表情が曇る「大丈夫だよ」と声をかけても、安心してくれないそんな経験はありませんか? 子どもとの関係において、「言葉」はもっとも身近で強力なツールです。ですが、同じ言葉でも、その伝え方次第で、心に響くこともあれば、反発や不信感につながることもあります。 今回は、子どもの心に届く「響... -

子どもにとって「社会性」は学力よりも大切?──幼少期から育てる対人力
「うちの子、友達との関わりが苦手で…」「勉強はできるけど、集団行動になると戸惑ってしまう」 保護者や教育者のあいだで、こうした声をよく耳にします。 近年、子どもたちの育ちのなかで特に注目されているのが「社会性」です。学力や技術だけでなく、人と協力し、自分を表現し、他者と関係を築く力が、生涯を通して子どもの幸福感に大きく... -

子どもにとって「お盆」はどんな意味を持つのか──心を育てる日本の伝統行事
夏休みの一大イベントのひとつ、「お盆」。多くのご家庭で、祖父母の家に帰省したり、お墓参りに出かけたりすることでしょう。 大人にとっては馴染み深いこの行事も、子どもにとっては「なぜやるのか」「何のための時間なのか」がわかりにくく、形式的になりがちです。 しかし実は、お盆は子どもの“心を育てるための絶好の機会”でもあるので... -

「言語の本質」とは何か?──子どもに言葉を教える前に知っておきたいこと
「もっとはっきり話しなさい」「ちゃんと伝えないと、相手にはわからないよ」そんなふうに、子どもに言葉づかいを正そうとする場面は、日常の中に多くあります。 ですが、「言葉」を教える前に、私たち大人が一度立ち止まって考えたい問いがあります。 それは、「そもそも言語とは、何のためにあるのか?」ということです。 今回は、子どもの... -

子どもが学校に行きたくなる理由はどこにある?モチベーションの本質と家庭でできる支援とは
「どうして学校に行きたくないの?」「やる気がないのは甘えじゃないの?」 学校へ行くことに前向きになれない子どもを見て、そう思ってしまう保護者の方は少なくありません。 しかし、子どもが学校に行くモチベーションには、見えづらい心理的要因が深く関係しています。この記事では、子どもの学校生活におけるモチベーションの仕組みと、... -

親族が集まるとき、子どもの“心”が育つ──感情を交換する場の大切さ
親戚が集うお正月、お盆、法事、冠婚葬祭──。こうした「親族の集まり」は、現代では少しずつ減少傾向にあるものの、子どもにとっては非常に貴重な学びと心の育ちの機会です。 本記事では、なぜ“親族の集まり”が大切なのか、そしてその場で交わされる「感情の交換」が、子どもの社会性や人間関係力をどう育てるかについて、教育と発達心理の視...