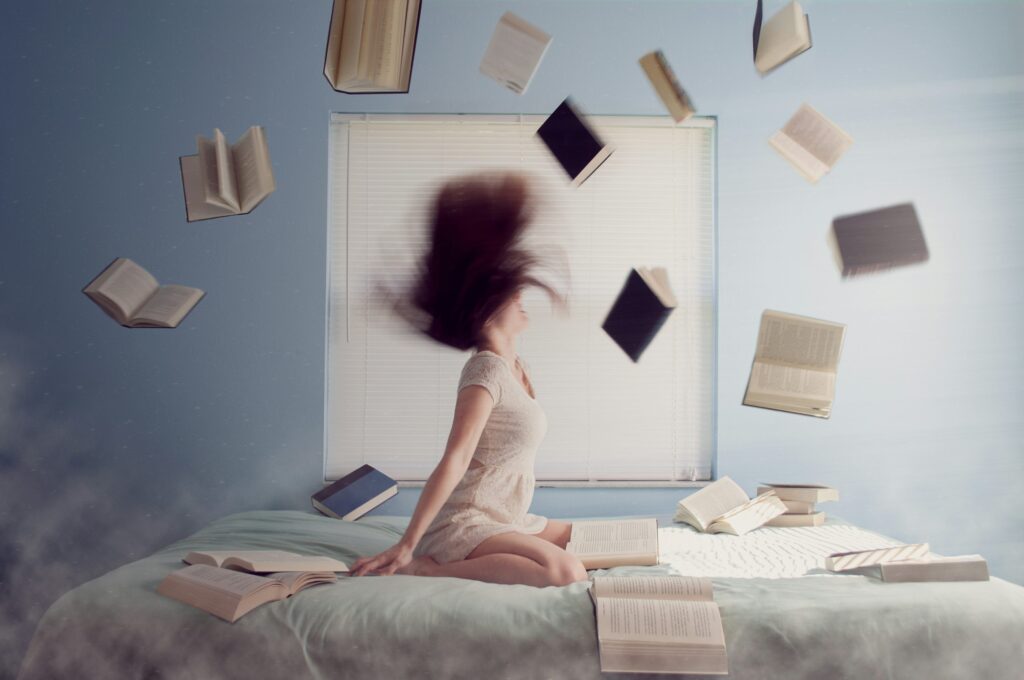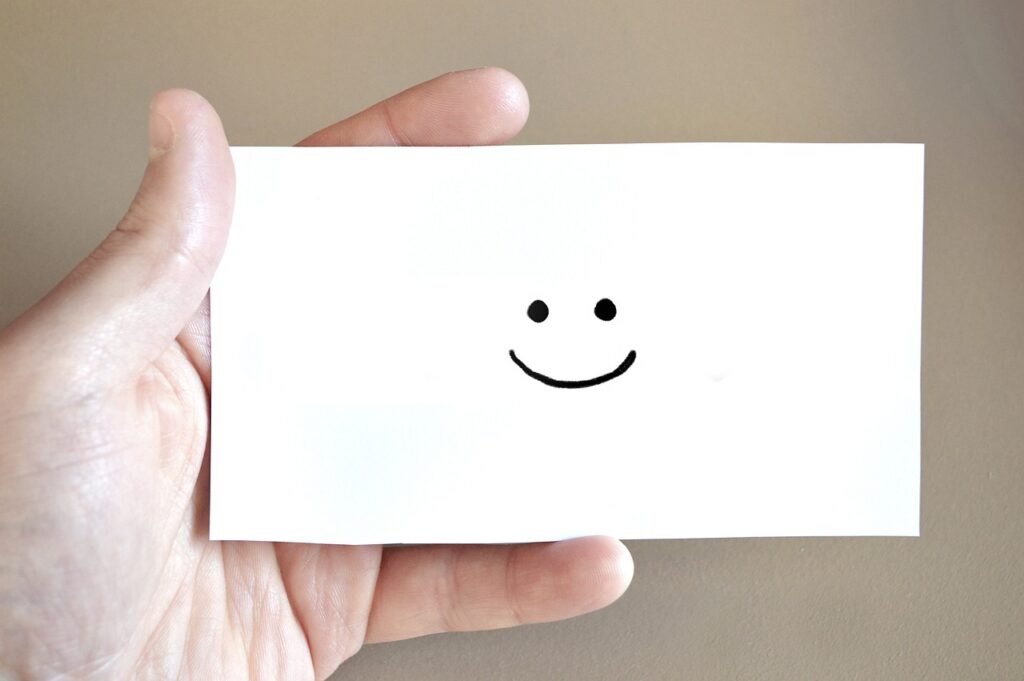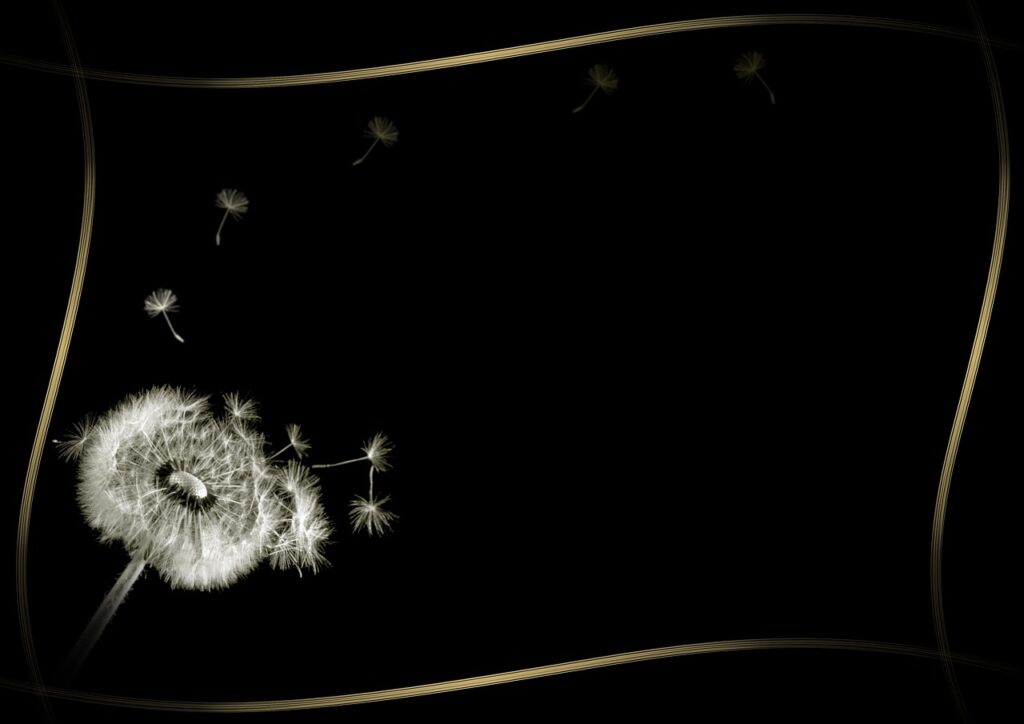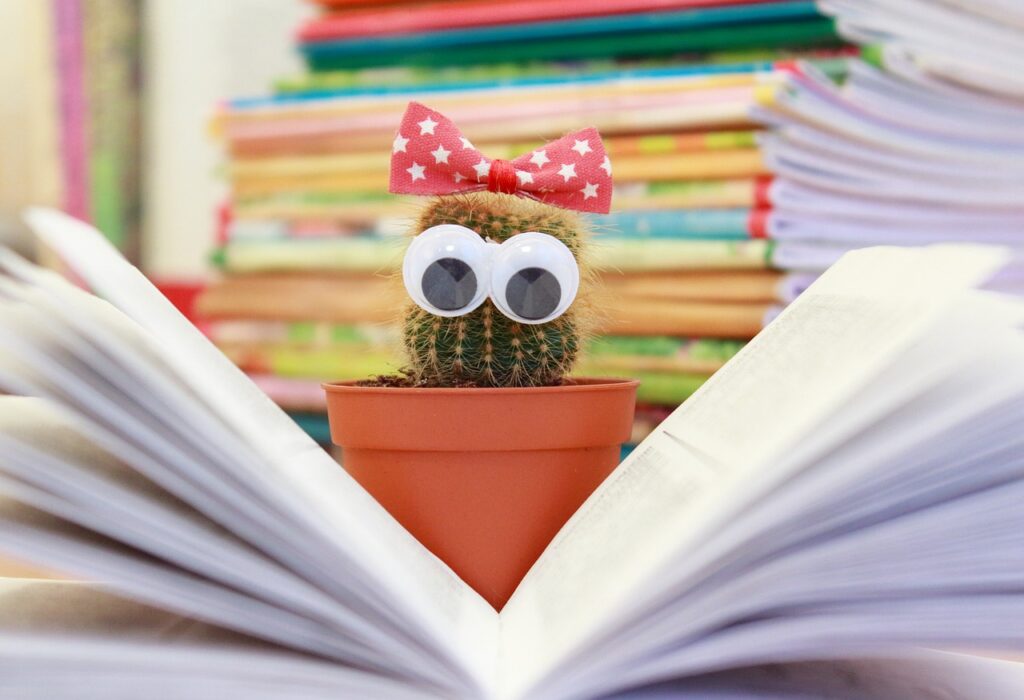発達– category –
幼児期から小学生・中学生にかけての発達段階に応じた課題と接し方をまとめています。年齢に合ったサポートで、健やかな成長を支援しましょう。
-

子どもの心技体をバランスよく育てるには|非認知能力・体力・知力を総合的に伸ばすために
子どもの成長を支えるキーワードとして注目されている「心技体」。スポーツだけでなく、生活や学習、人間関係など、あらゆる場面で大切な考え方です。 この記事では、子どもが心も体も技もバランスよく育つために、家庭や教育の現場でできる具体的な関わり方を紹介します。非認知能力の育成や、体力・学力の土台づくりにもつながる内容です。... -

【年齢別 子どもへの関わり方 声かけ 育児】親子関係を深めるステップとは
子どもの発達には段階があります。その発達段階に応じた「関わり方」を意識することで、子どもとの信頼関係はぐんと深まります。 本記事では、乳児期から思春期までの年齢別の関わり方のポイントを具体的に解説します。声かけ、接し方、距離の取り方の参考にしてください。 0~2歳(乳児期):安心感を育む「まるごと受容」 この時期の子ども... -

静かに聞く、静かに待つ:子供の成長を支える大人の役割
「静かに聞く、静かに待つ」という姿勢は、親や教育者にとって非常に重要です。 特に、子供が自分の気持ちを表現する際や、学習テーマに対して興味を持ち始める時期には、「待つ」ことが大切です。 子供が忙しい生活の中で、自分たちの気持ちを整理する時間を作ることは難しきですが、大人がその中で「静かに聞く」「静かに待つ」という姿勢... -

子どもが「約束を破った」とき、どう指導するかで信頼関係が変わる
子育てや教育の現場で、「ちゃんと約束したのに守らなかった」「また嘘をついた」「信じていたのにがっかり」という場面に出くわすことがあります。そんなとき、大人が感情的になったり、過剰に叱責してしまうと、子どもが本当に学ぶべき「約束の意味」を理解するチャンスを逃してしまうことがあります。 この記事では、「約束を破った子ども... -

子どもがかんしゃくを起こしたとき、まず親が落ち着くべき理由とは?
「もうやだ!」「なんでわかってくれないの!」おもちゃを投げる、地面に寝転がる、大声で泣きわめく── 子どもがかんしゃくを起こす場面は、どの家庭でも日常的に起こり得ます。その瞬間、親の頭に浮かぶのは「どうしたらいいの?」という戸惑いと、「早く収めたい」という焦りかもしれません。 この記事では、子どもがかんしゃくを起こす理... -

発育発達期におけるけが:成長期の子どもの健康を守るために
発育発達期、特に小学生から高校生にかけての時期は、子どもたちの身体と心が急速に成長する重要な時期です。 この時期に経験するスポーツ活動や日常生活は、将来の健康状態や生活習慣の基盤を築く機会であると同時に、発育中の身体に過度な負担がかかり、さまざまなけがが発生しやすい時期でもあります。 この記事では、発育発達期の子ども... -

「言葉にしない伝え方」が子どもを伸ばす?ビジュアルコミュニケーションの力
言葉を使わなくても、子どもと深くつながれる方法があります。それが「ビジュアルコミュニケーション(視覚的コミュニケーション)」です。 子どもが言葉でうまく伝えられないとき、視覚的な表現や非言語のメッセージは、コミュニケーションの大きな支えになります。 今回は、教育や子育ての場面で活用できる「ビジュアルコミュニケーション... -

「聴く力」は育てられる──受動的な聴き方と能動的な聴き方の違いとは
「ちゃんと話を聞いてるのに、なんだか通じない」「子どもが私の話をまったく聞いていない気がする」 家庭や教育現場でこんな経験をしたことはありませんか? それは、単に「聞いている」つもりでも、本当に“聴けている”わけではないからかもしれません。人の話を聴くには、「受動的な聴き方」と「能動的な聴き方」の2つがあります。 本記事... -

「相手は自分と違う」──その気づきが子どもの心を育てる
「なんであの子はそうするの?」「わたしなら絶対にしないのに」。そんな言葉が子どもから聞こえてきたら、それは社会性の成長が始まっているサインかもしれません。 子どもたちは成長の過程で、「自分と相手は違う存在である」という事実に何度も直面します。この気づきこそが、思いやり・共感・協調性といった人間関係の土台を築く第一歩で... -

魅力的なフィジカルリテラシーの世界へようこそ!子どもの成功の鍵を握る力を育むために
フィジカルリテラシーという言葉を聞いたことがありますか?現代の教育において、見逃せない大切なコンセプトです。 本記事では、フィジカルリテラシーが子どもの成長にどのように役立つか、具体的な方法とともに詳しく解説します。この記事を読むことで、あなたのお子さんが今後どのように成長し、成功していくのかのビジョンが広がることで... -

言葉にしない「伝え方」──非言語コミュニケーションで気をつけたいこと
言葉にしなくても、私たちは多くを伝え合っています。まなざし、身振り、声のトーン、距離感……それらすべてが非言語コミュニケーションです。 特に子どもとの関わりでは、大人の表情や態度、ちょっとした“間”が子どもに強い印象を与えることがあります。 本記事では、非言語コミュニケーションにおける注意点について、心理学的な視点を交え... -

「相手を尊重する」──子どもの人間関係を育てる土台
「ちゃんと友だちと仲良くしてね」「人の気持ちを考えて行動しようね」 保護者や先生が日々、子どもたちに伝えるこの言葉。でも、その“本当の意味”を、子どもたちはどれくらい理解しているでしょうか? 子どもにとって「相手を尊重する」とは、単なるマナーや礼儀の話ではありません。それは、自分と違う他者の存在を肯定しながら、安心して... -

子どもにとって「社会性」は学力よりも大切?──幼少期から育てる対人力
「うちの子、友達との関わりが苦手で…」「勉強はできるけど、集団行動になると戸惑ってしまう」 保護者や教育者のあいだで、こうした声をよく耳にします。 近年、子どもたちの育ちのなかで特に注目されているのが「社会性」です。学力や技術だけでなく、人と協力し、自分を表現し、他者と関係を築く力が、生涯を通して子どもの幸福感に大きく... -

親族が集まるとき、子どもの“心”が育つ──感情を交換する場の大切さ
親戚が集うお正月、お盆、法事、冠婚葬祭──。こうした「親族の集まり」は、現代では少しずつ減少傾向にあるものの、子どもにとっては非常に貴重な学びと心の育ちの機会です。 本記事では、なぜ“親族の集まり”が大切なのか、そしてその場で交わされる「感情の交換」が、子どもの社会性や人間関係力をどう育てるかについて、教育と発達心理の視... -

順調なときより、つまずいたときにこそ「その人らしさ」は現れる
私たちは日々の子育てや教育支援のなかで、子どもがうまくいっているときの姿を喜び、誇りに思います。けれど本当に大切なのは、うまくいかないときに、どんなふうにふるまえるかではないでしょうか。 「良くないときにこそ人間性が出る」。この言葉は、大人だけでなく子どもにも深く関係しています。 学習につまずいたとき、友達との関係に... -

子どもの心を支えるのは、日々の「言葉の栄養」です
「どうせムリ」「また失敗したの?」そんな言葉は、大人が思っている以上に子どもに深く突き刺さります。一方、「大丈夫、きっとできるよ」「がんばってるね」といったポジティブな言葉は、子どもの心を温かく包み、自信や前向きな行動につながっていきます。 本記事では、子どもにポジティブな言葉を掛けることの意味とその効果、実践の工夫... -

子どもも大人も大切にしたい「人間関係をよくするための基本」
人間関係は、学校でも家庭でも、社会でも避けては通れないものです。「友達とうまくいかない」「先生や親と話すのが苦手」そんな悩みを抱えている子どもたちは少なくありません。 しかし、人間関係はセンスや性格ではなく、「育てる力」です。今回は、人との関係をより良くするために、子どもにも伝えたい「基本の考え方」と「実践のヒント」... -

なぜ「悲しみ・怒り・不安」に寄り添うことが大切なのか?──ネガティブ感情こそ受け入れる意義
子どもが泣いたり、怒ったり、落ち込んだり──。そうした「ネガティブな感情」に直面したとき、私たち大人はつい「泣かないで」「そんなことで怒らないの」などと、気持ちを抑え込もうとしてしまうことがあります。 しかし実は、ネガティブな感情ほど、共感し、受け入れることが子どもの健やかな心の発達に不可欠だと、心理学や発達支援の分野... -

表情の豊かさは、心の豊かさにつながる力
あなたの身近に、表情で気持ちが伝わる子どもはいませんか?笑顔がこぼれたり、目が輝いたり、ちょっとした表情の変化から心の内が感じ取れる子。そうした子どもたちは、周囲との関係づくりがスムーズで、自己表現も豊かであることが多いです。 一方で、こんな相談も少なくありません。「うちの子、何を考えているのかわかりづらいんです」「... -

子どもに伝えたい「ちょうどいい距離感」──人間関係は“つかず離れず”がいちばん
友達とずっと一緒にいたい、でも少し疲れるときもある。仲良くしたいのに、べったりされると苦しくなる。 子どもたちは日々、友人関係の中でこうした「人との距離感」に悩みながら成長しています。 本記事では、人間関係を心地よく保つための“つかず離れず”という考え方を、どう子どもに伝えるかについて、心理学や発達段階をふまえて具体的...