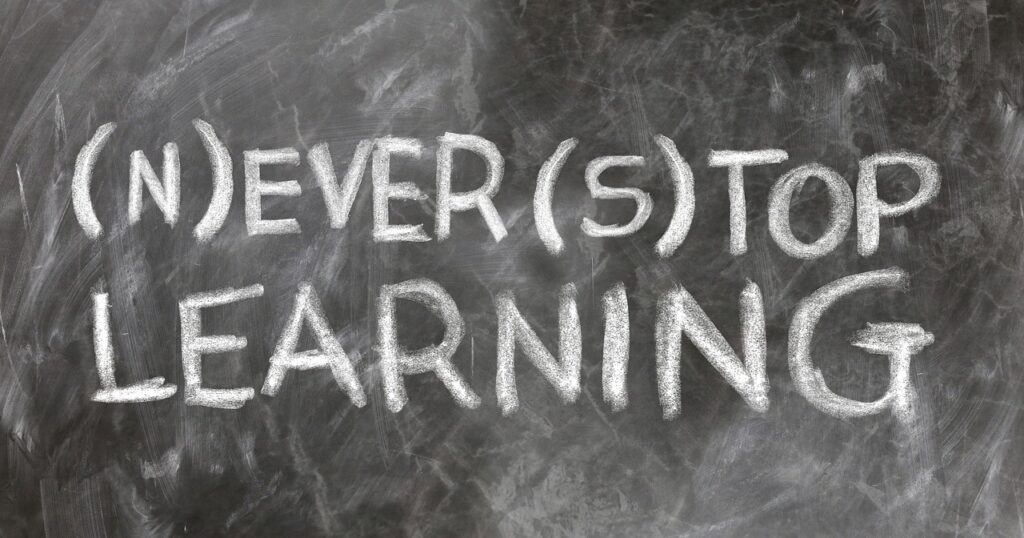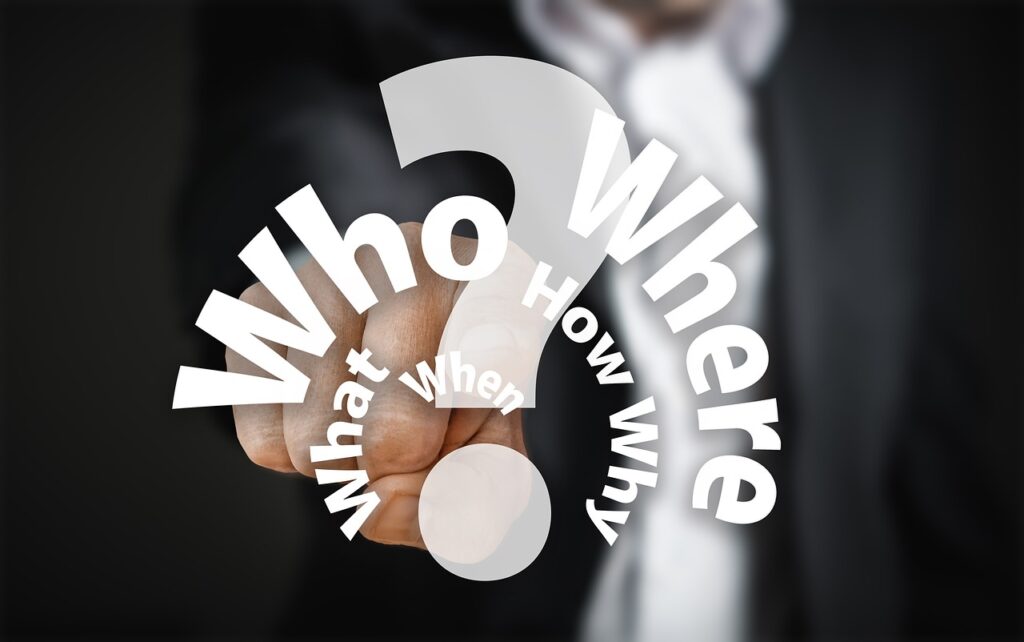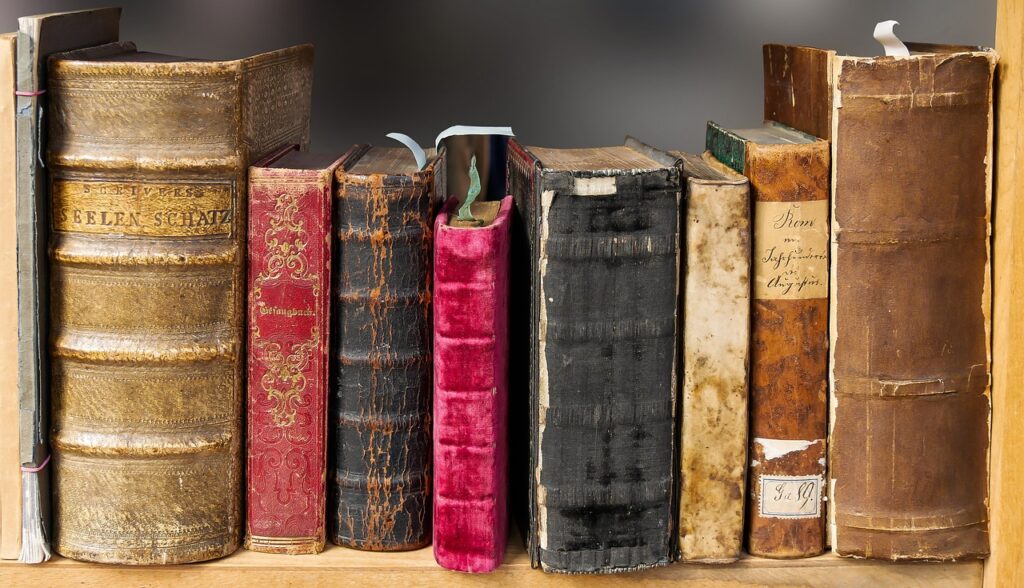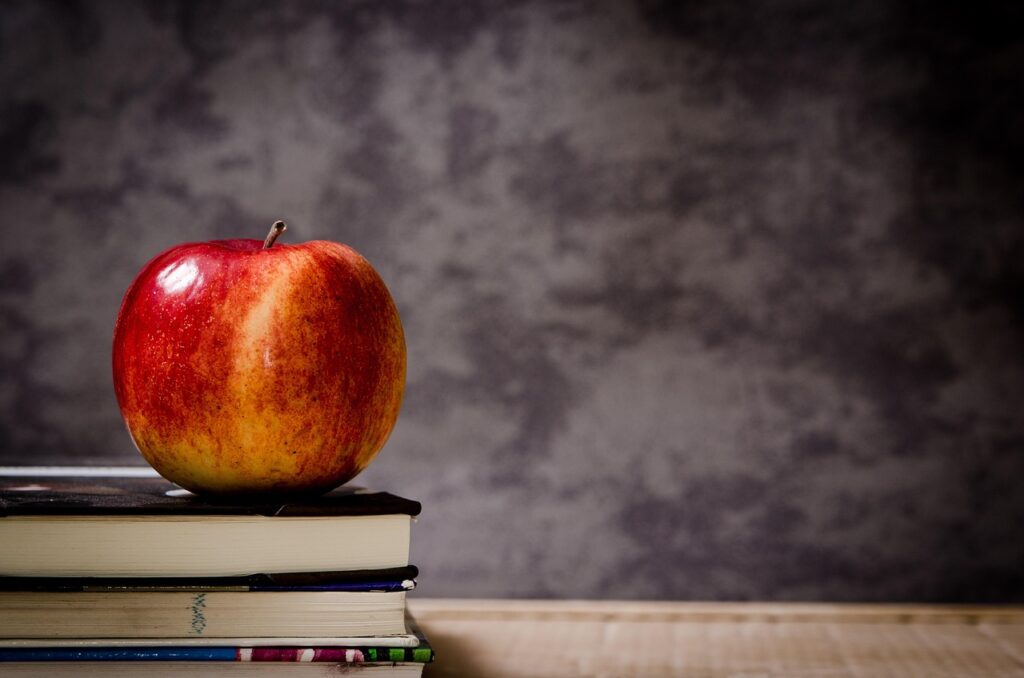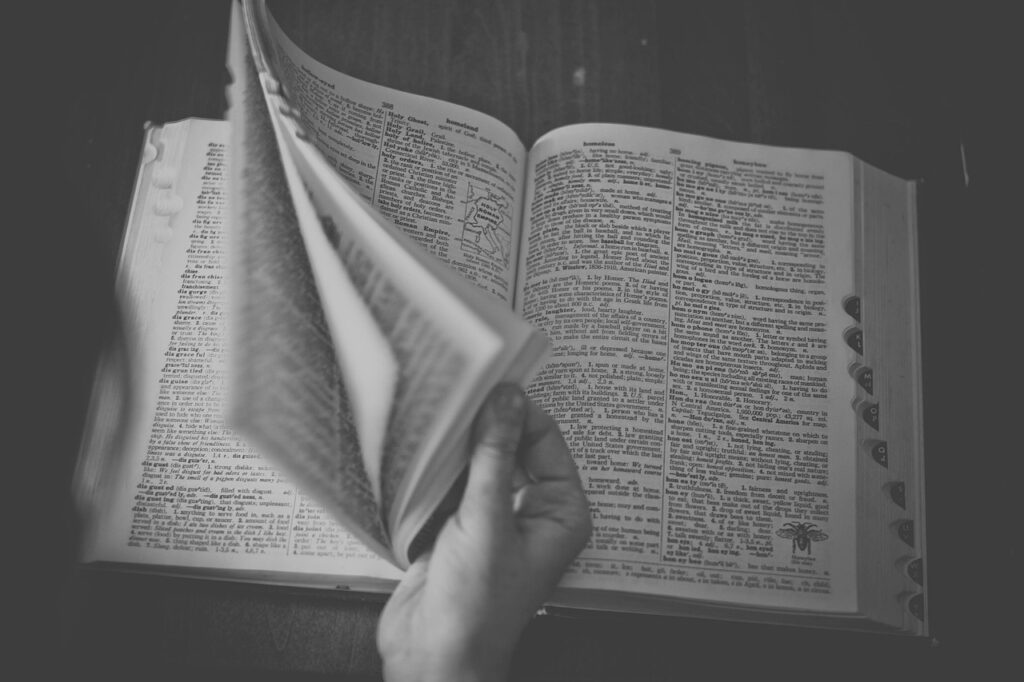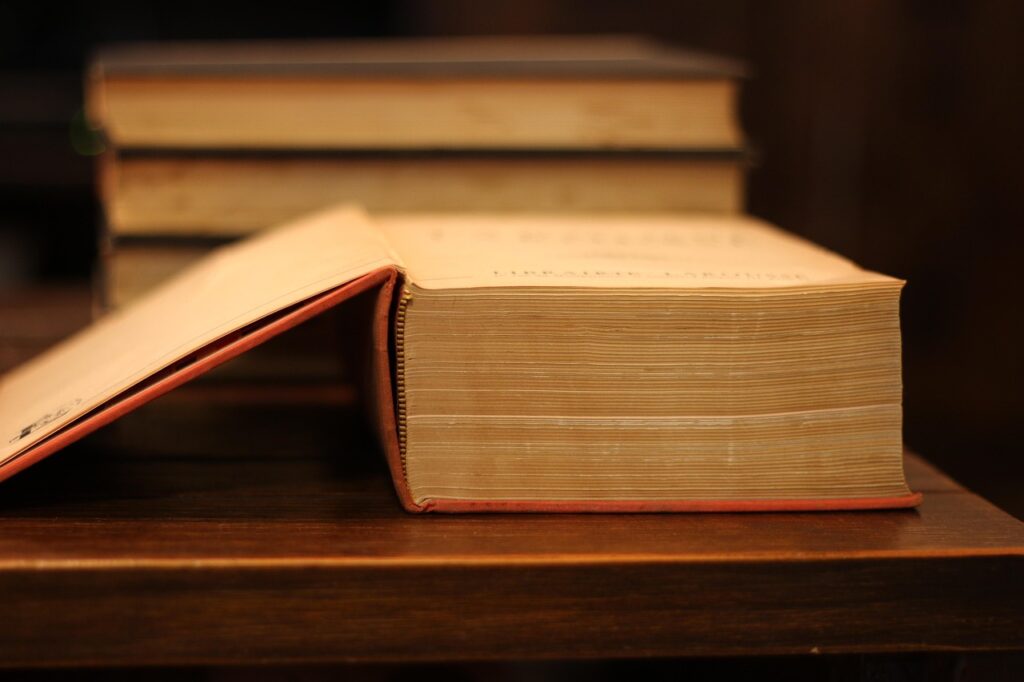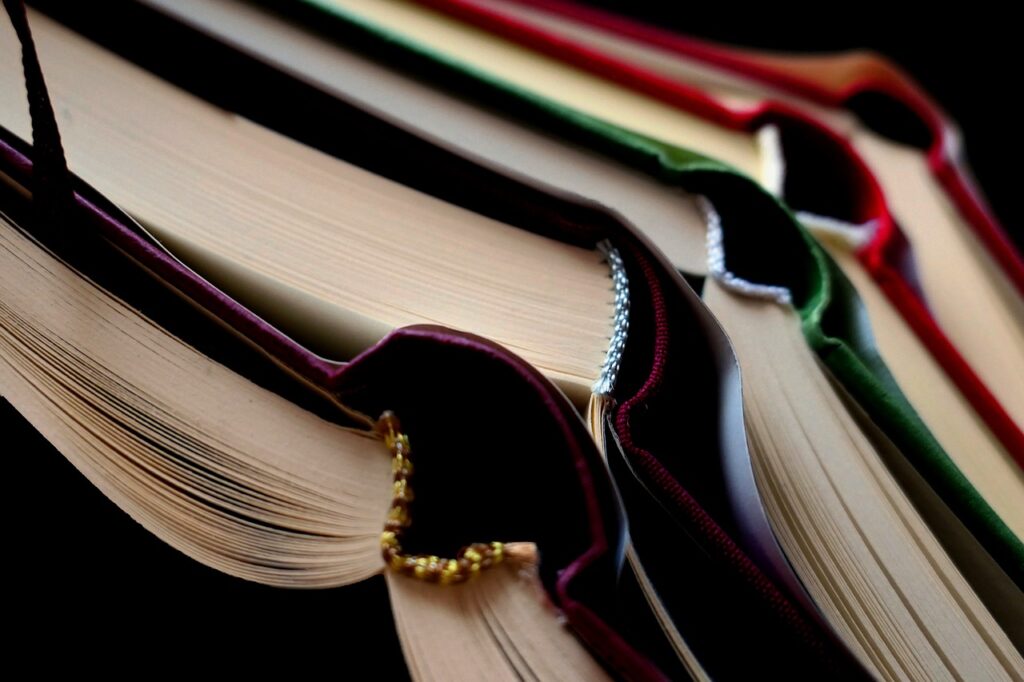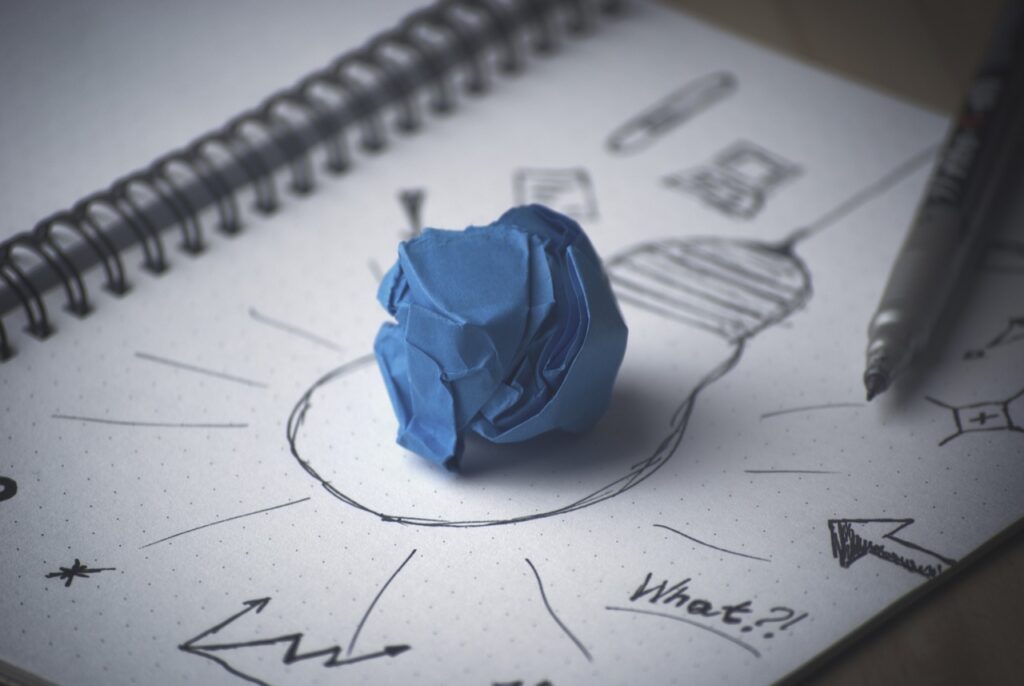学習– category –
お子さまの学び方に合った勉強法や家庭でできる学習支援の工夫をご紹介します。発達段階に応じて、無理なく学習習慣を育てましょう。
-

「その子だけの視点」と「その子だけの答え」を大切に育てるには
「子どもには、自分なりに物事を捉える力を持ってほしい」「型にはまらず、オリジナルな考え方ができる子になってほしい」そんな願いを抱く保護者や教育者の方は多いと思います。 けれど実際には、正解を求められる学習環境や、他者と比較される日常の中で、子どもたちは「自分の見方でいい」と思えなくなっていくことも少なくありません。 ... -

問題解決の力を育てる「水平思考」と「垂直思考」とは?
子どもが問題にぶつかったとき、どんなふうに考えるでしょうか。答えを一つに絞って正解を探すタイプもいれば、自由な発想で多くの可能性を探るタイプもいます。その違いは、思考のスタイル、つまり「垂直思考」と「水平思考」に表れます。 本記事では、教育の現場や家庭で活用できる水平思考と垂直思考の違い、バランスの重要性、そして育て... -

情報があふれる時代に欠かせない「メディア教育」とは
現代の子どもたちは、生まれたときからインターネットやスマートフォンが身近にある「デジタル・ネイティブ世代」です。SNS、動画サイト、ニュースアプリ、AIチャットなど、日常的に多くのメディアに触れる環境に生きています。 そんな中で今、教育現場や家庭で注目されているのが「メディア教育」です。 この記事では、なぜ今メディア教育が... -

考える力と非認知能力の関係とは?今、子どもの未来に必要な力を見直す
非認知能力とは何か? 「非認知能力」とは、テストの点数やIQのように数値では測りにくい、意欲・協調性・自制心・忍耐力・好奇心・自己効力感(自分にはできるという感覚)などの心の力を指します。 認知能力が「知識を覚え、計算し、答える力」だとすれば、非認知能力は「それを活用しようとする力、失敗しても続ける力、人と関わりながら... -

「ずるい!」と感じる心が育つとき──公正・公平の価値を子どもに伝えるには
子どもが友達とのやりとりで「ずるい!」と感じる場面は、成長の過程でよく見られます。それは、「自分と他人の扱いの違い」や「正しさ」に対する感受性が育ち始めている証拠でもあります。 しかし、「公正・公平」が何かを具体的に理解するには、知識だけでなく、体験や対話が必要です。大人の一方的な教えではなく、子ども自身が「なるほど... -

【年齢別の集中時間の目安】子どもの集中力 を育てるために知っておきたい基準
子どもが集中してくれない…。それは「集中力がない」のではなく、年齢に応じた集中の持続時間を超えているだけかもしれません。 集中力には年齢による限界があります。大人と同じような持続時間を期待してしまうと、子どもも疲れてしまい、学習が苦手になる原因にもなります。 今回は、子どもの年齢別に見た集中できる時間の目安と、家庭でで... -

子どもに必要な「自問自答する力」とは?思考力と自己理解を深める育て方
自問自答できる子が伸びる理由 子どもが「どうしてこうなったのかな?」「これでよかったのかな?」と自分に問いかける習慣は、学力だけでなく人間力を育てるうえで欠かせません。このような自問自答の力は、単なる反省や迷いではなく、思考力・判断力・自己理解力の土台です。 特に現代のように正解が一つではない時代において、自分で考え... -

【集中力を高める方法】#子ども #集中力 #家庭学習 に効く環境と声かけのコツ
「うちの子、集中力がなくて…」「すぐ気が散ってしまう…」そんな悩みを抱えていませんか?子どもの集中力は、生まれつきの性格ではなく、適切な関わりや環境づくりによって育てることが可能です。 この記事では、子どもの集中力を高めるために、今すぐできる実践的な工夫をご紹介します。 集中力とは「一時的な能力」ではなく「育てる力」 集... -

子どもの「学び」を正しく見取るには?──これからの時代に必要な学習評価の視点と方法
「うちの子、どれだけ理解できているのだろう」「テストの点だけで、学びが評価できるのだろうか?」 子どもの学びを支える立場として、保護者や指導者が持つべき重要な視点のひとつが「学習評価」です。しかし、従来の“点数”や“平均”だけでは、子どもの成長を正しく捉えられない場面も増えてきています。 本記事では、これからの時代に求め... -

【学習効率を上げる方法】子どものやる気と集中力を引き出す環境づくり
子どもの学習効率を高めたい――これは、多くの保護者や教育関係者が共通して抱く願いです。しかし、学習時間を増やしても成績が上がらない、すぐに集中が途切れる、やる気が続かない…こうした悩みを抱えている家庭は少なくありません。 この記事では、子どもの「学習効率」を科学的・実践的な視点から高めるためのヒントをご紹介します。これ... -

「言葉にする力」が子どもの未来を変える——言語化することの本当の意味とその育て方
「なんとなくモヤモヤする」「よくわからないけどイライラする」——そんな風に感じている子どもに、「どうしたの?何があったの?」と問いかけても、うまく言葉にできない姿を目にすることがあります。 今、子どもたちにとって「言語化する力」はますます重要になっています。この記事では、子どもの言語化能力を育む意義とその方法について、... -

問題解決に必要な「2つの思考法」──ラテラルシンキングとロジカルシンキングの違いとは?
子どもたちが生きていくこれからの社会は、変化が激しく、正解がひとつとは限らない時代です。そんな中で注目されているのが、「ラテラルシンキング(水平思考)」と「ロジカルシンキング(論理的思考)」という2つの異なる思考法です。 本記事では、それぞれの思考法の違いと特徴を分かりやすく解説し、子どもの発達や教育にどう活かせばよ... -

探求心を育てるためには|好奇心・問い・体験が鍵になる学びの原動力
「なぜ?」「どうして?」「これ、やってみたい!」そんな言葉が子どもから自然に出てくるとき、そこには確かな「探求心」が育ち始めています。探求心は、学び続ける姿勢や問題解決能力、創造性の源。AI時代の子どもたちにとって欠かせない力です。 この記事では、探求心を育てるために家庭や教育現場でできる工夫を、具体例を交えてご紹介し... -

語彙力が未来をつくる?子どもにとって「言葉の力」が必要な理由
子どもが「話せない」「伝えられない」「わかってもらえない」―― こうした困難の背景にあるのが、「語彙力(ボキャブラリー)」の不足です。語彙力とは、知っていて使える言葉の数と質のことを指します。 幼児期から学童期、そして思春期にかけて、語彙はその子の世界の広さを決める鍵となります。 この記事では、「語彙力はなぜ必要か?」と... -

子どもの「学びの軸」をつくるために、今なぜ“歴史基準”が重要なのか
子どもが育っていく中で、「何を学ぶべきか」「どんな力を身につけるべきか」という問いは、保護者や教育関係者にとって常に悩ましい問題です。教育内容や学習方法は時代とともに変化しますが、変わらない基準がひとつあります。それが「歴史を基準にする」という視点です。 この記事では、子どもの教育において歴史を基準に考えることの意味... -

クレバーな子供を育てるには|思考力・判断力・好奇心を伸ばす家庭の関わり方
「クレバーな子ども」とはどんな子? 「クレバー(clever)」という言葉には、単なる頭の良さ以上に、状況を見抜く力・柔軟な判断・言語化する力・人間関係をうまく築く力などが含まれます。学校のテストで良い点を取るだけではなく、「どう考えるか」「なぜそう判断するか」といった、本質をつかむ力がクレバーな子どもの特徴です。 こうし... -

考える力を育てるために必要なことは?子どもが主体的に学ぶために親ができること
考える力とは何か? 「考える力」とは、情報をただ受け取るのではなく、自分で疑問を持ち、整理し、意味づけていく力です。この力は、国語や算数など教科の枠を超えて、社会生活や人間関係の中でも発揮される、生きていくうえで不可欠な力です。 特にこれからの時代は、知識の多さよりも、どのように考え、判断し、選び取るかが求められます... -

自己評価できる子どもに育てるには|子どもの自信と成長を支える家庭での関わり方
なぜ「自己評価」が重要なのか? 自己評価とは、「自分ができたこと・できなかったことを、自分で見つめて考える力」のことです。 これは、学力やスキル以上に人生を支える力といわれる非認知能力のひとつです。「今の自分をどう見るか」「どこを伸ばしたいか」「何を頑張ったか」を振り返ることで、子どもは自らの成長を実感し、次への行動... -

子どもが「学校以外」でも学ぶ理由とは?――学びの多様化を正しく理解する
近年、子どもたちが学校だけでなく、塾や通信教育、オンライン学習など、さまざまな場で学ぶ光景が当たり前になってきました。保護者の中には、「学校で十分では?」「あれもこれも詰め込みすぎでは?」と感じる方もいるかもしれません。 しかし、現代の子どもたちにとって、学校以外での学びは“補完”ではなく“必然”になりつつあります。この... -

子どものボキャブラリーを豊かにするには?今すぐできる5つの習慣
言葉は思考の器――。 この言葉が示すように、子どもが物事を理解し、考え、表現していくうえで、「語彙(ボキャブラリー)」の豊かさは欠かせない力です。語彙力が高い子は、自分の気持ちを整理しやすく、他者との意思疎通もうまくいきます。 逆に、語彙が不足すると「わかっているのに言えない」「思いが伝わらない」といったコミュニケーシ...